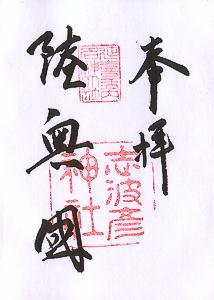[HOME] >
[神社記憶] >
[北海道東北地方] > [HOME] >
[神社記憶] >
[北海道東北地方] >
|
|
|
志波彦神社
しはひこじんじゃ
宮城県塩竈市一森山1−1

|
|||
|
式内社 陸奥國宮城郡 志波彦神社 名神大 |
宮城県塩竈市にある。
JR東北本線塩釜駅の北1.5Km、仙石線本塩釜駅の西1Km。
鹽竈神社と同一の境内に鎮座している。
鹽竈神社の東参道に朱塗りの鳥居があり、
周囲の紅葉は非常に美しい。
鹽竃神社と志波彦神社の中間地点にある境内図 |
 |
創立年代は不詳。
通称、冠川明神、志波道上宮。
社名の読み方は、「しはひこ」「しわひこ」「しばひこ」など、
資料によって異なるが、鹽竈神社でいただいた由緒には「しはひこ」とあった。
明治までは、七北田川(冠川)の畔、
仙台市宮城野区岩切に鎮座していたが、
明治7年、鹽竈神社別宮に遷祀、昭和13年、現在地に遷宮された。
祭神は、志波彦神とされているが、志波(しは)と鹽(しほ)の読みから
鹽土老翁神とする説がある。
神紋は通常、鹽竈桜とされているが、
朱塗りの鳥居には、尾長の三つ巴が付いていた。
鹽竈桜は、八重桜の中心に三枚の細い葉があるもの。
堀川天皇は、このような桜を歌に詠んだ。
あけ暮れてさぞな愛で見む塩釜の
桜が下の海士のかくれ家
大鳥居  | 大鳥居  |
参道から神門 |
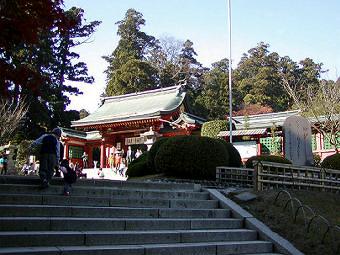 |
神門  | 拝殿  |
拝殿  | 拝殿内部  |
本殿 |
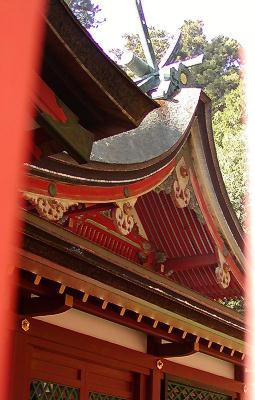 |
|
志波彦神社
志波彦神社は鹽竃の神に協力された神と伝えられ、
国土開発・産業振興・農耕守護の神として信仰され
ている。当神社はもと、仙台市岩切冠川(七北田川)
の畔に鎮座され、陸奥国延喜式内社百座のうち名神
大社として、朝廷の厚い信仰があった。明治四年
五月国幣中社に列格されたが、境内も狭く満足な祭
典を行うことが不可能な為に、明治天皇の御思召に
より、明治七年十二月二十四日に鹽竃神社の別宮に
遷し祀られた。さらに、昭和七年国費を以って御造
営することになり、昭和九年現社地に工事を起し、
明治・大正・昭和三代にわたる神社建築の粋を集め
竣工し、昭和十三年九月に遷座した。本殿・拝殿何
れも朱漆塗り、彫刻部分は極彩色漆塗りで、昭和
三十八年塩竈市の文化財に指定された。
−参道案内より− |
【 志波彦神社(印刷用ページ) 】