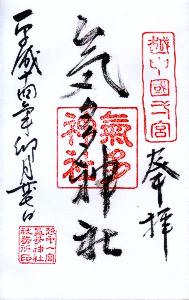[HOME] >
[神社記憶] >
[北陸地方] > [HOME] >
[神社記憶] >
[北陸地方] >
|
|
|
氣多神社
けたじんじゃ
富山県高岡市伏木一ノ宮字大平2063

|
|||
|
式内社 越中國射水郡 氣多神社 名神大 |
富山県高岡市にある。
伏木駅の北西2Kmほどの一ノ宮に鎮座。
緩やかな坂道を登ると、境内入口の階段。
階段上の境内には、「かたかごの丘」という苔と木々に覆われた場所があり、
越中国総社跡の伝承地となっている。
二上山の東麓の高台に位置し、南南東1Kmに国衙跡とされる古古府がある。
また東南500mには国分寺跡とされる薬師堂があり、
越中国の中心部に位置している。
よって、当社は越中国一宮と称し、地名も一ノ宮。
越中には、一宮と自称する神社が四社あるが、その一つ。
国府の移動や、勢力の変化によって、一宮も変遷したのだという。
他の一宮は、高瀬、射水、雄山の三社。
社伝によれば、養老元年(717)、能登・気多大社からの勧請。
能登は、養老2年(718)に越前から分立し、天平13年(741)越中に合併。
その時点で、能登の気多大社が、越中全体の一宮であった。
その17年後の、天平宝字元年(757)に、再度分立しているため、
その頃に、国府に近い当地に、分霊を祀ったものと考えられている。
延喜式には、「名神大社」とあるが、写本によっては
射水神社が名神大社となっており、混乱が見られる。
『白山記』には、二上(射水)と新気多が勢力争いをして、
新気多が勝ち、一宮となったとあるらしい。
大げさな玉垣などもなく、非常にオープンな境内で、
華やかさはないが、静かで落ち着いた神社だ。
神紋は、多分、境内の神馬像についていた剣梅鉢。
前田利常の祈願所であった。
社号標のある階段を上ると、鳥居があり、平坦な境内。
右手に「かたかごの丘」と書かれた一角があり、
木の鳥居の奥に、「越中国総社跡伝承地」とかかれた碑が建っている。
境内入口  | 参道の清泉  | 参道の鳥居  |
境内の「かたかごの丘」にある総社跡伝承地 |
 |
境内  | 神馬像  |
参道を歩き、さらに階段を上ると、正面に拝殿。
左手には、新しい境内社・大伴神社がある。
本殿は、永禄年間に再建されたもので、国の重要文化財。
簡素な境内に、簡素な社殿だが、なかなか風格のある本殿だ。
境内社・大伴神社  | 階段上に社殿  | 拝殿扁額  |
社殿 |
 |
本殿  | 拝殿  |
|
気多神社 単立 高岡市伏木一ノ宮二〇六三 氷見線伏木駅二粁 祭神 大己貴命・奴奈加波比売命 建物 本殿三間社流造(室町期建・重文) 拝殿 由緒 養老二年能登の気多大社から勧請、越 中一ノ宮と称した。神亀二年聖武天皇から神 領の寄進をうけ、延喜式では国幣の小社に列 した。越中国司大伴家持も厚く崇敬し、当時 は社殿も広壮であった。その後兵火で焼失し、 別当僧宥応が小祠を建て祭祀をつづけていた が、正保二年領主前田利常が社殿を再建、社 領を寄進しその祈願所とした。境内は樹林が 多く幽寂のたたずまいにあふれている。 −『全国神社名鑑』− |