 [HOME] >
[神社記憶] >
[関東地方] > [HOME] >
[神社記憶] >
[関東地方] >
|
|
|
近津神社
ちかつじんじゃ
茨城県久慈郡大子町下野宮1626

|
||
茨城県大子町にある。
下野宮駅の北、下野宮小学校の裏側に狭い道を隔てて、南面して鎮座。
当地は、久慈川と八溝川の合流する地点にあり、
八溝川を遡ると八溝山、久慈川を遡ると福島白川郡へと続く。
雨の早朝の参拝で、境内は暗く、社殿や参道には灯りが灯っていた。
拝殿の灯りが、ジオン公国モビルスーツの眼のような感じ。
あるいは、おおきなダースベーダ。
巨大な社殿が意志を持っているようで、面白かった。
社伝によれば、文武天皇慶雲4年(707)の創建という。
藤原富得の夢に神が現われ、白羽の矢を授け、
「吾近津明神なり、八溝山の悪鬼を除去せしむるを得たり」と告げた。
この夢を奏上し、当社が創建された。
八溝山から流れる八溝川の下流に位置し、
八溝山の麓・上野宮にも近津神社が存在する。
上野宮の近津を上宮とし、下野宮の当社を下宮、町付の近津神社を中宮として、
「近津三社」と呼ばれており、八溝山の麓社群を構成していたと考えられる。
当社の鎮座地は、稲村とも呼ばれており、「稲村三社」とも呼ばれていたことから、
当社は、式内・稲村神社の論社でもあるが、
当時この地は陸奥に属しており、常陸の式内社とは考えにくいらしい。
「近津三社」については、
久慈川の流れに沿って位置する、
棚倉町馬場の都々古別神社(上宮)と棚倉町八槻の都々古別神社(中宮)、
下野宮の当社・近津神社を総称して、「近津三社」と呼ぶ場合もあり、
両都々古別神社が、陸奥一宮であることから、当社も、陸奥一宮群に加える考えもありえるか。
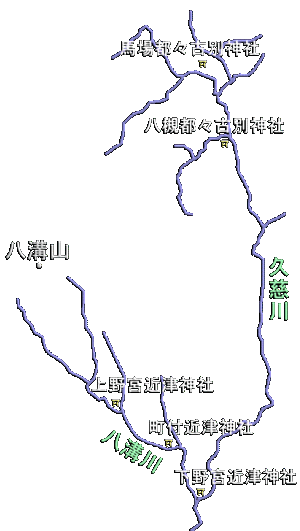
「近津」の字義に関しては、近くに祀ったお宮であるというのが一般的だが、
この神社鎮座地を見ると、川の合流地点という意味も見えてくる、ような気がする。
そういう意味では、当社は「大近津」であり、重要な神社であるとも考えられる。
拝殿の脇には、「鉾杉」という御神木の大杉が聳えている。
創建当時に植えられたと伝えられる杉で、
前九年の役(1051)、後三年の役(1083)の阿部氏の乱の時、
八幡太郎義家が、武運長久・戦勝祈願のため当社に参籠し、
持っていた鉾を、この杉に立てかけたという杉。
境内入口  | 参道と神門  | 義家手植えの都々母杉  |
境内 |
 |
社殿  | 社殿  |
境内社  | 本殿  | 金精様  |
境内社  | 境内社  |
|
郷社 近津神社
祭神 級長津彦命 面足命 惶根命創建は社傳に拠るに、文武天皇慶雲四年、藤原富得、夢に神あり、白羽の矢を授けて曰く、吾近勝明神なり云 云と、因て八溝山の悪鬼を除去せしむるを得たりと、此事奏上に及びしかぱ、勅して此地に社を営ましめら る、是れ本社の創建なりと云ふ、本社は、元と陸奥に属し、彼の陸奥白川郡馬場近津明神の下宮なりと、後小 松天皇應永十三年四月源兼保、地三千貫を寄奉る、但、之れ義家の例に依ると、次いで永正十一年六月、佐竹 義治更に六百五十貫の地を寄せ奉りしが、徳川氏天下の権を握るに至り、社領三十六石八斗、及除地十五石 八斗三升四合を寄奉る、明治維新一度村社に列せしが、後九年郷社に列す。 社殿は本殿、拝殿、其他神楽所あり、本殿は神明造りにして南に面す、壮麗にあらざるも瀟洒却て神威の高き を仰がしむ、境内は千二百七十五坪(官有地第一種)及近く編入せられし上地林二反七畝十七歩より成る、「前 に八溝川を控ヘ、後に八溝山を負ふ、而かも東西老檜天を蔽ふ、蓋、自然の神地たり。 −『明治神社誌料』− |







