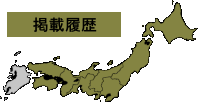[HOME] >
[神社記憶] >
[九州地方] > [HOME] >
[神社記憶] >
[九州地方] >
|
|
|
西寒田神社
ささむたじんじゃ
大分県臼杵市野津町西寒田神尾392

|
||
|
式内社 豊後國大分郡 西寒多神社(大) |
大分から10号線を南下。
57号線と合流する犬飼から道なりに進み、2Km。
左手の脇道を登り、さらに2Kmほど進む。
3つの集落を通過し、道がカーブしている所に数件の家がある。
その家の横、農家の庭先にでも出るような道を登る。
暗くて急な道を登りつめると、開けた丘の上に出る。
そこにある。そこまでは、案内や、鳥居などはない。
社名を記したものも見あたらず、やや不安の中、参拝した。
社殿左後方の石碑に、薄く「延喜式内社」の文字が見える。
参拝後、麓の民家を訪問し、社名を確認させていただいた。
鳥居扁額には、「鎮國一宮」とある。
文化九年、白川神祇伯より「鎮國一宮」の社号を受けている。
社名を確認させていただいた方は、
鳥居扁額を「豊後國一宮」の意味だとおっしゃっていた。
当社を大分郡へ遷し、現在の豊後國一宮西寒多神社としたという説がある。
その根拠は、延喜式に「大野郡 西寒多神社」と書かれているため
本来は、大野郡鎮座の当社であるとする。
ただし、他の写本ではすべて「大分郡 西寒多神社」とあり、
『式内社調査報告』では、当社の式内社・西寒多神社説を否定している。
小雨の中、暗くて急な登り坂を登る。
登りの先が明るくなり、燈籠らしきものが見え、
鳥居が見えた時には、感激した。
とにかくわかりにくい場所にあるのだ。
社域 |
 |
鳥居  | 鳥居扁額 「鎮國一宮」  | 参道  |
本殿  | 拝殿  |
境内の石碑 読めなかったが延喜式に関する記述のようだ |
 |
冒頭部分に「延喜式」云々とある  | 社殿  |
|
『太宰管内志』には延喜式に大野郡西寒多神社
あり、とあり。『亀山随筆』には西寒多紳杜は初大野郡野
津ノ荘寒田村にあつたのを傅へによると、大友能直十世ノ
孫式部大輔親世、応永七年、将軍義満により従四位下九州
節度便に補せられたとき、応永十年三月この神社を、居城
の南に移して、この地を寒田と名づけたとある。その後大
野郡寒田の方は衰へ、今は祭日の定めもなく、神官なども
絶え、僅かに一茅宇が残るだけになつたとある。しかし
〔稲生云〕として大野郡西寒田神社は社を再興して、鳥居
廻廊などを建立したとある。『豊後國志』も大野郡寒田神
社を西寒多神社とし、応永十五年大友親世が大分郡植田に
移し寒田と名づけた。とあり、今は一茅宇になつてゐると
ある。「社格昇進願」によると、延喜式などにふれ、中世
社運が衰へたが、江戸時代臼杵藩の崇敬をうけ延享(一七
四四〜八)の頃鶴峰但馬を神職とし、文化九年(一八一二)
白川神紙伯の「鎮國一宮西寒田神社」の社号をうけてゐ
る。この年臼杵藩、十一月十日の祭礼を復し、岡藩等の領
民も参加した。文化十二年社殿の建立を許され、文化十四
年(一八一七)神道長上より「西寒田神社」の社号をうけ
た。文政元年(一八一八)拝殿鳥居廻廊が造営され、以後
祭礼も盛になつたとある。明治六年村社、昭和十五年社格
昇格運動を起したが、成就しなかつた。
−『式内社調査報告』− |
【 西寒田神社 】