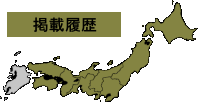[HOME] >
[神社記憶] >
[九州地方] > [HOME] >
[神社記憶] >
[九州地方] >
|
|
|
白沙八幡神社
はくさはちまんじんじゃ
長崎県壱岐市石田町筒城仲触1012

|
|||
壱岐空港の北1Km。筒城仲触にある。
広大な筒城浜を横切る道路脇に、
大きな白い鳥居があり、参道が西に延びる。
参道には、少し小振りの鳥居(他では普通)があり、
社叢の山へ参道が続く。
午前中の参拝で、朝の太陽を正面から浴びた
白くて大きな鳥居が、印象的だったが、
参道を振り返って見た、そのシルエットがまた美しい。
境内は、それほど広くはないが、
社域は広大。神社としての「大きさ」を感じる。
社記によれば、宇佐神宮からの勧請で、
社殿は宇佐の方向(辰、東から南へ30度)を向いている。
ただし、『壱岐神社誌』によれば、石清水からの勧請とある。
八幡勧請以前は、筒城宮あるいは管城宮と呼ばれ、
海神の娘・玉依姫命を祭神とする、海神社であった。
延宝の橘三喜による式内社調査によれば、
近くにある現・海神社が、式内社・海神社に比定されているが、
その後の諸説では、当社が式内社・海神社とされている。
当社の社叢は、椎を優先種とする自然暖帯林で、
長崎県指定天然記念物となっている。
壱岐七社参拝の一社。
七社とは、白沙八幡・興神社・住吉神社・本宮八幡・箱崎八幡・国片主神社・聖母宮。
参道の先に階段があり、その上が境内になっている。
境内には、八幡なのに三猿の石像があった。
周辺の神社から持って来たんだろうか。
神紋は、八幡なので三つ巴なのだが、
境内にあった昔の瓦には菊水もついていた。
拝殿内には、「韓櫃石」という石が安置されている。
由緒や謂れはわからなかった。
大鳥居  | 参道から鳥居  | 境内から参道  |
参道と社域 |
 |
境内  | 社殿  |
拝殿  | 拝殿内、台の下に韓櫃石  |
本殿  | 拝殿  | 本殿  |
境内の三猿  | 境内の石祠  |
|
〈由緒沿革〉
「社記」に、「当社は六国史所載の社にして、桓武天皇
延暦六年卯八月三日豊前国宇佐郡より異賊降伏国家擁護
の神として八幡大社に勧請せられたり依って大神殿は辰
の方向に建立せるものなり。」又、「醍醐天皇延喜五年乙
丑十二月二十六日勅宣同月二十八日御神体を此の国に渡
し奉る。」とある。 『壱岐名勝図誌』に、「古老、伝云昔城列の八幡より渡 り給いし時逆風にて此処の海浜に御船がかりし給うこと 七日、故に其処を神瀬と云う、水主は夕部の浦人なり。 かくして陸に上りまして浜辺の清水にて御水にて御手を 洗い給う。故に其の水を名附けて御手洗と云う(又京水 とも云う)、其処に人ありて諸神に向いて曰、大神は何時 渡らせ給いしやと、答給わく、タ部渡りしと、故に其処 を夕部といえり。其より長岳と云う丘に登り給いて村内 の景色を見そなわして曰、東に清水あり南に蓬来あり西 に和泉あり北に福小路ありつつき徳満崎に宝珠ある村な りと讃め給いしと、其の時神功皇后は右田境の海浜に着 給い陸に上りましし時髷を落し給う故に共の瀬を髷瀬と 云う、今かも瀬と云うは転語なり、又錦の御衣を干し給 う仍て其処を名付けて錦浜という。此の時大神内山(現 在社地)に降り致りまして底津宮根に宮柱太敷立て鎮座 せられたり」と伝う。 当社は壱岐国大七社の一として古来国民の崇敬する 所、例祭には国主直参の社にして崇敬特別なりしも廃藩 以後一列の村社となれり。 一 明治九年十二月四日改めて村社加列 一 大正四年十二月二十八日神饌幣帛料供進指定神社となる。 一 昭和七年八月十七日郷社に列せらる。 一 同九月十六日神饌幣帛料供進指定神社となる。 「当社拝殿内に縁由ある石あり。長さ四尺三寸二分、 横二尺八寸一分、高さ二尺三寸六分、板敷上現所高さ九 寸五分韓櫃石の名称あり。古より拝殿改築に際し人々敬 懼して除く事能わざる也。 −『石田町史』− |
【 白沙八幡神社 】