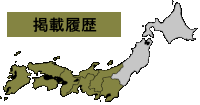[HOME] >
[神社記憶] >
[北海道東北地方] > [HOME] >
[神社記憶] >
[北海道東北地方] >
|
|
|
母也明神
ぼなりみょうじん
岩手県遠野市松崎町松崎矢崎

|
|
|
御祭神 |
遠野市松崎町にある。
遠野駅の北5Kmほどの矢崎。
猿ヶ石川の西の丘の中腹に鎮座。
入口は、道路から少し入った場所で、最初、見落としてしまった。
入口に案内板があるのだが、狭い山道の道が上に続いている。
100mほど登ると、小さな小屋のような祠と鳥居がある。
|
松崎村の字矢崎に、母也堂(ぽなりどう)という小さな祀がある。 昔この地に綾織村字宮ノ目から来ていた巫女があった。 一人娘に婿を取ったが気に入らず、さりとて夫婦仲はよいので、 ひそかに何とかしたいものだと思って機会を待っていた。 その頃猿が石川から引いていた用水の取入れ口が、 毎年三、四間がほど必ず崩れるので、 村の人は困り抜いていろいろ評定したが分別もなく、 結局物知りの巫女に伺いを立てると、 明後日の夜明け頃に、白い衣物を着て白い馬に乗って通る者があるべから、 その人をつかまえて堰口に沈め、 堰の主になってもらうより他にはしようもないと教えてくれた。 そこで村じゆうの男女が総出で要所要所に番をして、 その白衣白馬の者の来るのを待っていた。 一方巫女の方では気に入らぬ婿をなき者にするはこの時だと思って、 その朝早く婿に白い衣物をきせ白い馬に乗せて、隣村の附馬牛へ使いに出した。 それがちょうど託宣の時刻にここを通ったので、 一同がこの白衣の婿をつかまえて、堰の主になってくれと頼んだ。 神の御告げならばと婿は快く承知したが、 昔から人身御供は男蝶女蝶の揃うべぎものであるから、 私の妻も一緒に沈もうと言って、そこに来合わせている妻を呼ぶと、 妻もそれでは私も共にと夫と同じ白装東になり、二人でその白い馬に乗って、 川に駆け込んで水の底に沈んでしまった。 そうするとにわかに空が曇り雷が鳴り轟き、大雨が三日三夜降り続いた。 四日目にようやく川の出水が引いてから行ってみると、 淵が瀬に変わって堰口に大きな岩が現われていた。 その岩を足場にして新たに堰を築き上げたので、 もうそれからは幾百年でも安全となった。 それで人柱の夫婦と馬とを、新堰のほとりに堰神様と崇めて、 今でも毎年の祭りを営んでいる。 母の巫女はせっかくの計らいがくいちがって、 かわいい娘までも殺してしまうことになったので、 自分も悲しんで同じ処に入水して死んだ。 母也明神というのはすなわちこの母巫女の霊を祀った祠であるという。 −『遠野物語拾遺 第二十八話』より− |
遠野の巫女を祀った祠。
自然の驚異と、人間の小賢しい謀の物語りだ。
母也と書いて「ぼなり」と読む。
遠野の地名にはアイヌ語の痕跡が多いようだが、
元はどういう意味だったのだろう。
一説には、ボナリやオナリは、巫女を意味する古代語だそうだが、
イナリ(稲荷)にも通じるのだろうか。
社殿の右手に、巫女塚への細い道が示されていたが、行ってみる気になれず。
また、矢崎の堰に祀られた堰神様があるらしいが、そちらには行き忘れた。
なんとも中途半端な参拝になってしまった。
社殿と鳥居 |
 |
狭い登り口  | 巫女塚への道。 距離が書かれていれば行ったかも。  |
|
母也明神の由来
矢崎堰(せき)は、大同年間(一、一八〇年
前)に造られたと伝えられる。昔、矢崎の巫女(みこ)がいた。一人娘に 婿を取ったが気に入らず、何とかしたいもの だと機会を待っていた。その頃、猿ヶ石川か ら田に水を引く堰の止めが、毎年大水の為に やぶられ、困りぬいた村人達は巫女に伺いを たてた。ここぞとばかり巫女は、「神のお告げ だ、白い着物を着て白い馬に乗って通る者が あるから、その人を堰口に沈め、堰の主にな ってもらうしか方法がない」と教えた。 一方、巫女は気に入らない婿に白い着物を 着せ、白い馬に乗せ隣村に使いに出した。村 中を通りがかったその婿を見た村人は「堰の 主になってくれ」と頼んだ。 婿は運命とあきらめ快く承知したが、それ を知った巫女の娘である妻も白装束になり、 男蝶女蝶の二人揃ってこそ真があると、二人 で白い馬に乗って、堰口に沈んだのである。 その後大雨が降り、堰口に大きな二つの岩 が現われ、村人はこれを足場に止めを築いた。 巫女は、可愛い娘まで失った事を深く悔み悲 しんで毎日泣き暮れ、同じ場所に入水して死 んでしまった。 堰には、主となった夫婦と、白馬を祀る堰神 様があり、巫女の屋敷跡に巫女の霊を祀った のが母也明神であると伝えられており、巫女 塚は巫女の墓と伝えられている。 −社頭案内板より− |
【 母也明神 (遠野) 】