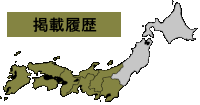殺生石稲荷神社
せっしょうせきいなりじんじゃ
福島県大沼郡会津美里町宮林甲4377−4

福島県会津高田町にある。
伊佐須美神社の南、道を隔てた隣り、宮川に面して鎮座。
伊佐須美神社の末社の一つだ。
案内板によると、創祀年月は不詳。
天保十二年に、殺生石の祟りを鎮めるために再興された。
殺生石は、栃木県の温泉神社の側にあり、
中国から渡ってきた妖狐が、三浦介、上総介に退治された後、
毒石となったもの。
会津示現寺の開祖源翁和尚が、その毒石を打砕いたため、
破片が各地に飛び散ったという伝説がある。
その破片の一つが、当地に飛来した、この殺生石。
打砕かれてもなお、人に害をなしたと考えられており、
当地の天変地異も、この石のせいにされていたようだ。
狭い境内、玉垣の中に、小さな本殿と、左横に岩がある。
社前の案内では、殺生石を祀った神社とあるが、
これが殺生石だろうか。
玉垣内の石、これが殺生石か?
|
 |
|
殺生石稲荷神社の由来
| 御祭神 | 宇迦魂神(うかのみたまのかみ) |
| 鎮座地 | 大沼郡会津高田町宮林甲四三七七ノ四番地 |
| 御祭日 | 毎年二月初午の日 毎月一日 月首祭 |
| 由 緒 |
当神社の創始は中古の頃か、詳らかでないが、天保年間
殺生石の霊を慰め災害をなくしようと、祭祀を
復興した。爾来壱百六十年会津開拓の祖神
を祀る伊佐須美大神と相倶に、普く庶民の崇敬を
専らにし、殖産興業、商売繁昌に霊験灼かな神
として敬仰されてきた。
然るに昭和の現代特に終戦後、思想の混迷と神祇
崇敬の念哀微とに加えて、御社殿の老朽化甚だしき
ため、久しく高天原の渡御殿を仮宮に奉遷してい
たが、天皇陛下御即位満五十年の佳辰を記念して
奉賛会を組織、篤志家の浄財によって御社殿を
造営し、祭祀を興隆した。維時、昭和五十一年十二月二十日也。
|
| 殺生石の由来 |
昔から宮川の氾濫と落雷と火災とは、当地の住民にとって
最も畏怖すべき天変地異であり、災難であった。
伊佐須美神社の御手洗であり、川として左程大きくない
宮川の洪水に多くの犠牲者が出るのは、殺生石の祟りで
はなかろうかと、その恐怖は幾代か語り継がれてきた。
ある時、在村の藩役人三村某が発願し、村人と共に
その霊を手厚く祀ったのが、天保十二年(一八一一年)
この時、水神も亦奉祀された。(この水神社は、当社の南手
瓢箪池の側に立つ赤鳥居の神祠がそれで、数年前
再建、祭祀は復興した。祠に天保十二年の刻印がある)
ところでこの殺生石は、至徳二年(一三八三年)会津の
名僧源翁和尚が、人民を苦しめていた殺生石を
説伏、教化した際に打砕かれた化石の一つが、会津
のこの地に飛来してきたと傳えている。栃木県那須
湯本温泉神社近くには、今尚湯煙りが立ち込め、
毒気を朶んだ岩石が「史蹟殺生石」として
保存されている。
|
−社頭案内板より−
|
 [HOME] >
[神社記憶] >
[北海道東北地方] >
[HOME] >
[神社記憶] >
[北海道東北地方] >