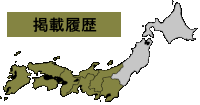[HOME] >
[神社記憶] >
[北海道東北地方] > [HOME] >
[神社記憶] >
[北海道東北地方] >
|
|
|
コンセイサマ
こんせいさま
岩手県遠野市土淵町

|
||
|
御祭神 |
遠野市土淵町にある。
遠野駅から340号線を北東へ6・7Kmの場所。
340号線に案内があるので、案内に従って奥へ進むと、
行き止まりの場所に到着。そこが境内。
遠野では有名な観光地なので、誰に聞いてもわかると思う。
境内には社殿が一つ。
社殿の横に、変わった形の石(リンガ?)が置かれていたが、
これもコンセイサマの一種だろうか。かなり大きい。
社殿の中に、男根形の石神が祀られており、
これが、昭和47年に発見されたコンセイサマ。
境内には、男女の性器の形の石もあり、
ここまでの道にも幾つかの男根石がある。
遠野には、このように男根の形の石神が多く祀られている。
有名なところでは、ここ山崎のコンセイサマ、程洞のコンセサマ、荒川の金勢社など。
遠野では、コンセイサマ同様、駒形社でも男根石を祀るようで、
その違いは明確ではない。
コンセイサマの神徳には、3種類あり、
子宝の神、婦女子の病気平癒、馬の息災を願う。
|
コンセサマを祭れる家も少なからず。 この神体はオコマサマとよく似たり。 オコマサマの社は里に多くあり。 石または木にて男の物を作りて捧ぐるなり。 今はおひおひとその事少なくなれり。 −『遠野物語 第十六話』より− 土淵村から小国へ越える立丸峠の頂上にも、昔は石神があったという。 今は陽物の形を大木に彫刻してある。 この峠については金精神の由来を説く昔話があるが、 それとよく似た言い伝えをもつ石神は、まだ他にも何か所かあるようである。 土淵村字栃内の和野という処の石神は、 一本の石棒で畠の中に立ち、女の腰の痛みを治すといっていた。 畠の持主がこれを邪魔にして、 その石棒を抜いて他へ棄てようと思って下の土を掘って見たら、 おびただしい人骨が出た。 それで崇りを畏れて今でもそのままにしてある。 故伊能先生の話に、石棒の立っている下を掘って、 多くの人骨が出た例は小友村の蝦夷塚にもあったという。 綾織村でもそういう話が二か所まであった。 −『遠野物語拾遺 第十六話』より− |
興味深いのは、『遠野物語拾遺』の記述。
コンセイサマには男根形の他に、石棒のものがあり、
荒川の金勢社も石棒だそうだ。
畑の中の石棒の下には多くの人骨が埋まっており、
石棒(石神)の持つ、「生と死」の側面を象徴しているようだ。
遠野に多く祀られる石神信仰は、変化の無いものの象徴である石と
生産を意味する男根の融合により、死後の再生や不死への憧れを
示しているのだろうか。
いろいろと複雑な要素があり、興味深い。
境内 |
 |
社殿左のコンセイサマ  | 社殿内に祀られているコンセイサマ  |
社殿  | 境内の陰陽石  |
こっちが男で  | こっちは女  |
|
山崎のコンセイサマ
遠野には多くの素朴なコンセイサマが
子授けや豊作の願い神としてまつられ
ていますが、昭和47年に発見されたこ
のコンセイサマは高さが1.5メートル
もあって最大です。背後の山頂の賽の河原と一対にして、 中世の人びとは”死と再生の地上まん だら”をここにつくっていました。 −社頭案内板より− コンセイサマ
コンセイサマは、金勢様又は金精様と書
きます。子宝を願う婦女子が、ここに奉納
されている赤い小枕を一つ借りてきて腰元
に置き、願いが叶えられれば二つにしてお
返しするならわしです。御神体は、男性の象徴を現し、すべての 物事を神に結びつけた民間信仰に由来する もので、これは駒形信仰とも混同されるよ うになりましたが、本来は生産の神として 信仰されたもののようです。 (『遠野物語』 第十六話 参照)
−社頭案内板より− |
【 山崎のコンセイサマ 金精様 (遠野) 】