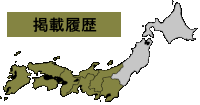[HOME] >
[神社記憶] >
[北海道東北地方] > [HOME] >
[神社記憶] >
[北海道東北地方] >
|
|
|
隠津島神社
おきつしまじんじゃ
福島県二本松市木幡字治家49

|
|
式内社 陸奥國安積郡 隠津嶋神社 |
福島県二本松市にある。
東北本線・安達駅の東12Kmほどにある木幡山の中腹に鎮座。
というより、木幡山全域が当社の神域。
木幡山の東にある、349号線から西へ登る車道を進むと
当社駐車場に到着するが、
当社の表参道は木幡山の西側を走る117号線(二本松川俣線)から入る道。
参拝は夏休みの初日。
宮城へ向かう途中に福島周辺を回る予定の最初に参拝。
いつも、神社参拝旅行の最初の神社と
最後の神社への参拝は、ちょっと特別な感じがする。
どの神社を最初にするか、最後にするかは
単にルート設定上での偶然に過ぎないのだが。
特に最初に参拝する神社へは期待が大きいのだが
当社は、その期待以上に良い雰囲気の神社。
境内も広大で、木々も豊富。
一日ゆっくりと時間を過ごしたい場所だが、
「最初」の神社なので、ゆっくりと過ごすことはできなかった。

木幡山へ向かう、木幡川に沿って東へ入る道を進むと
治陸寺の近くに北東の木幡山へ向いて、当社の一の鳥居が建っている。
一の鳥居 |
 |
一の鳥居から登っていくと、当社の遥拝殿。
遥拝殿の東側に階段の参道があり、二の鳥居が建っている。
本来なら階段を登って参拝したいところだが、
時間を短縮して、車で本殿の近くにある駐車場へ向かう。
遥拝殿 |
 |
遥拝殿  | 二の鳥居  |
広い駐車場の脇に、上へ登る立派な階段。
階段を登ると途中に東屋があり、
さらに登ると、門神社と木幡の大杉。
門神社社殿は、当社の旧本殿だったもの。
駐車場 |
 |
参道階段  | 大きな木  | さらに階段  |
門神社と木幡の大杉 |
 |
旧本殿だった門神社社殿  | 石碑が並ぶ  |
|
東和町指定文化財
昭和51年12月29日指定
丹波長次は丹羽長次か? −案内板より− |
門神社から参道を進むと道が別れ、一方の道の上に第一社務所。
もう一方に先には三重塔がある。
三重塔は現在、天満宮として祀られている。
三重塔の脇の階段を登ると当社社殿。
階段途中には医薬神社。
第一社務所 |
 |
天満宮の三重塔 | |
 |  |
社殿への階段  | 階段途中に医薬神社  |
|
福島県指定重要文化財(建造物)
隠津島神社三重塔
寛永二十年(一六四三)頃は、かろうじて初層の み形をとどめていたが、延宝二年(一六七四)、二 本松藩主丹羽光重が改築を行ない、享保元年(一七一 六)に再び修理を加えた。明治になって初層を残し て付近の倒木により破損したので、大修理を行なっ ている。初層は、総じて和様を基としている。 本県には、会津高田町の法用寺、いわき市の高蔵 寺に三重塔があるが、いずれも江戸中期以降のもの である。 −案内板より− | ||||||
階段を登ると正面に拝殿。
後方には流造の本殿がある。
本殿の右手には松尾神社。
左には岩の上に養蚕神社が祀られている。
社殿の左手の小道を進むと幾つかの境内社がある。
名前を確認したのは、養蚕大神社、八坂神社、疱瘡神社、白山神社。
その道をさらに進み、登っていくと木幡山経塚群があるのだが
僕は登っていない。
木幡山麓一帯が当社境内で、他にも羽山神社などがあるらしい。
社伝によると、
安積国造比止禰命の子孫・丈部直継足によって
神護景雲三年に勧請された古社。
大同年間、神仏習合して
隠津嶋神社弁財天と称したという。
文明・元和年間、領主大内家により社殿を造営。
蒲生家により杉の献植。
寛永十九年丹羽光重により安達東郷の総鎮守として
祭祀料五十石を献納された。
式内社・隠津嶋神社の論社の一つ。
旧社名は木幡山弁財天。
神仏分離後に厳島神社と改称し
明治三十五年、隠津島神社と改称した。
社殿 |
 |
拝殿  | 拝殿  |
養蚕神社と本殿  | 本殿と松尾神社  |
本殿脇の石  | 参道に並ぶ境内社  |
|
木幡山隠津島神社縁起
−境内案内板より− 木幡の幡祭り
毎年十二月の第一日曜日に行われる木幡の幡
祭りは、日本三大旗祭りの一つに数えられ、古
い歴史と伝統をもったお祭りです。白旗を先達
に赤、青、黄、緑と色とりどりの五反旗、百数
十本が勢ぞろいし、法螺貝を吹き鳴らしながら
木幡山の尾根を縦走します。この祭りは、平安中期天喜三年(一〇五五) 天皇の命を受けた源頼義と義家(八幡太郎) 父子が奥州の豪族、安倍氏を征伐した戦いの中 での出来事に由来しています。 戦いに敗れた源頼義父子は、僅かな兵と木幡 山に登り、戦勝祈願をしました。勝ちに乗じた 安倍氏は翌朝一気に決着をつけようとしました が、夜が明けると一驚。木幡山一帯は源氏の白 旗で埋まり、安倍氏の軍勢の数倍にもなってい たのです。さすがの安倍氏も攻撃を断念し急い で引き返しました。源氏の白旗と見えたのは、 実は木々に降り積もった白雪でした。 以来、神仏の加護を信ずる里の人々は、源氏 の白旗になぞり五反旗を手織り、木幡山を練り 歩きながら源氏の武勲を称えたと言うことです。 −駐車場の案内板− 参拝と御案内(由緒)
当神社は安積国造比祢命の後胤・丈部直継足の三男継宣が神護景雲三年(769 年)に隠津島神社を勧請した。後に式内社として延喜式神名帳に記載され、創立以来ここに千二百余年にわたり歴世の武将・国主・地頭・藩主が上下挙って尊信し、祭祀を厚くし、又一般庶民に至るまで信仰をあつめた。その後大同年間(806 年)に平城天皇の勅願によって弁天堂が建てられ、神仏混淆の社となり、この時より隠津島神社弁財天と称れるようになった。後世には木幡の弁天様と呼ばれ庶民に親しまれるようになった。天正十三年(1585年)伊達政宗の兵火により全山炎上、本社・末社悉く焼土となりしも藩主や庶民の信仰厚く、再建された。現存する本殿・拝殿は寛政元年(1789年)に二本松藩主丹羽長貴公の命により造営されたもので、実に十二年間の長き年月によって竣功された。明治に至っては初年の神仏分離令によって、別当治陸寺を廃し、厳島神社と称し明治三十五年神社名を復旧、隠津島神社と改称、明治四十年県社に列した。後の第二次世界大戦後、神道指令によって、宗教法人隠津島神社として届出、社格(元県社)解消となったが、今日現在においても平和・招福・知恵・縁結びの神と広く深く信仰されている。−『平成祭データ』− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参道や山道を歩いていると石に刻まれた石仏が目に入る。
木幡山には「木幡山三十三観世音」という観世音菩薩を刻んだ石が
三十三個あるらしい。
時間があったら全てを確認したかったが、今回は断念。
次回の楽しみにしておく。
ちなみに「木幡山三十三観世音」は以下のもの。
| 1.千手観世音菩薩 |
| 2.正観世音菩薩 |
| 3.十一面観世音菩薩 |
| 4.正観世音菩薩 |
| 5.正観世音菩薩 |
| 6.正観世音菩薩 |
| 7.千手観世音菩薩 |
| 8.十一面観世音菩薩 |
| 9.正観世音菩薩 |
| 10.千手観世音菩薩 |
| 11.馬頭観世音菩薩 |
| 12.十一面観世音菩薩 |
| 13.如意輪観世音菩薩 |
| 14.如意輪観世音菩薩 |
| 15.十一面観世音菩薩 |
| 16.十一面観世音菩薩 |
| 17.正観世音菩薩 |
| 18.千手観世音菩薩 |
| 19.子安観世音菩薩 |
| 20.正観世音菩薩 |
| 21.正観世音菩薩 |
| 22.正観世音菩薩 |
| 23.千手観世音菩薩 |
| 24.正観世音菩薩 |
| 25.馬頭観世音菩薩 |
| 26.正観世音菩薩 |
| 27.薬師堂竜泉寺 |
| 28.十一面観世音菩薩 |
| 29.正観世音菩薩 |
| 30.正観世音菩薩 |
| 31.正観世音菩薩 |
| 32.正観世音菩薩 |
| 33.正観世音菩薩 |
参道の上方の石に  | 参道脇の石にこんな感じ  |