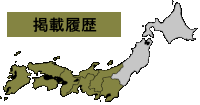[HOME] >
[神社記憶] >
[北海道東北地方] > [HOME] >
[神社記憶] >
[北海道東北地方] >
|
|
|
六神石神社
ろっこうしじんじゃ
岩手県遠野市青笹町中沢第17地割131

|
||
遠野市青笹町にある。
青笹駅から東へ、3Kmほど。
川沿いの道を中沢まで進み、舗装路が途切れたあたりから少し入った所。
当社は、六角牛山(1294m)山頂にある奥宮に対する神社。
大同二年に、奥宮に薬師、山麓に不動と住吉三神を祀ったが、
その後、嘉祥年代(848−851)に山麓の社を元住吉に遷座。
さらに、現在地に移る。
また、山頂の奥宮が、再三山火事の被害にあうため、
文治5年(1189)阿曽沼公石洞に新山宮として祀り、
さらに、当社に合祀し、明治になって六神石神社と改名。
というわけで、山麓だが、里宮というわけではなく「新山宮」。
大草里や赤沢に、六角牛神社里宮があるらしい。
どうして、当社だけ、六神石と改名したのかは不明。
六角牛山 |
 |
|
神の始 遠野の町は南北の川の落合に在り。 以前は七七十里とて、七つの渓谷各七十里の奥より売買の貨物を聚め、 其市の日は馬千匹、人千人の賑はしさなりき。 四方の山々の中に最も秀でたるを早地峰と云ふ、 北の方附馬牛の奥に在り。 東の方には六角牛山立てり。 石神と云ふ山は附馬牛と達曾部との間に在りて、 その高さ前の二つよりも劣れり。 大昔に女神あり、三人の娘を伴ひて此高原に来り、 今の来内村の伊豆権現の社ある処に宿りし夜、 今夜よき夢を見たらん娘によき山を与ふべしと母の神の語りて寝たりしに、 夜深く天より霊華降りて姉の姫の胸の上に止りしを、 末の姫眼覚めて窃に之を取り、我胸の上に載せたりしかば、 終に最も美しき早地峰の山を得、 姉たちは六角牛と石神とを得たり。 若き三人の女神各三の山に住し今も之を領したまふ故に、 遠野の女どもは其妬を畏れて今も此山に遊ばずと云へり。 −『遠野物語 第二話』より− |
鎮座の経緯は、やや複雑だが、結果的に
六角牛山と、母神を祀る伊豆神社を結ぶ線上に、当社が鎮座している。
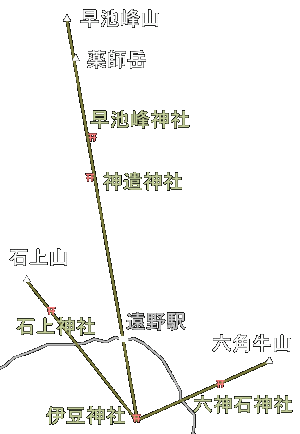
社殿の前にある灯篭に、菊の紋が付いていた。
正確には「八咫鏡」のような背景に「十六菊」。
さらに、菊の中心は丸ではなく、六角形になっていた。
鳥居をくぐると立派な参道が続く。
参道を歩き、階段を上ると、広くて綺麗な境内。
社殿も、新しい感じだ。
拝殿の額には、「六角牛新山宮」と書かれている。
社殿の左側後方に、「六角牛大神」とかかれた石碑がある。
六角牛山の奥宮の遥拝所だろう。
社殿の後方、一段高く本殿があり、本殿の周りにも
古峰、養蚕、大瀧、功徳などの境内社が並んでいる。
入口の鳥居  | 参道  | 参道  |
境内 |
 |
拝殿  | 神輿殿  |
古峯宮  | 本殿  | 大瀧社  |
養蚕宮  | 燈籠の神紋  | 功徳社  |
六角牛大神の石碑、遥拝所だろう |
 |
|
遠野三山の一つ六角牛山のふもとに鎮座し、表筒男命・中筒男命・底筒男命・息長帯姫命・大己貴命・少彦名命・誉田別命を祀る。
例祭日は旧8月15日であったが、現在は9月23日に行っている。 人皇第51代平城天皇の御代、大同2年(807)時の征夷大将軍坂上田村麻呂蝦夷地平定のため蒼生の心伏を願い神仏の崇拝をすすむ。時に六角牛山の頂に薬師如来、山麓に不動明王、住吉三神を祀る。爾来陸奥の国中の衆民、衆団をなして登山参拝あとを絶たず、霊山として山伏の修行者も多く集まる。 第54代仁明天皇の嘉祥年代(848−851)元住吉といえる地に社殿を建立し、住吉神を遷し奉り住吉太神宮と称す。 山頂の堂宇、再三の山火事に被災し、後鳥羽天皇の文治5年(1189)阿曽沼公石洞の地に神地を寄進して神殿を建立し、山頂の祭神を遷奉り六角牛新山宮と称し、六角牛山善応寺を創設し祭事を司掌させた。後に住吉太神宮の新座地を川向い(現在の六神石神社の地)に定め奉遷す。 寛文年中(1661−1673)南部領となるに及び社領95石を寄納される。六角牛新山宮は住吉太神宮に合祀される事となり、享保10年(1725)奉遷。明治5年(1872)六神石神社と改める。 −『平成祭データ』− |
【 六神石神社 (遠野) 】