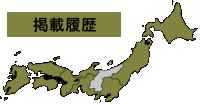[HOME] >
[神社記憶] >
[甲信越地方] > [HOME] >
[神社記憶] >
[甲信越地方] >
|
|
|
川會神社
かはあいじんじゃ
長野県北安曇郡池田町大字会染字十日市場12079

|
||
式内社 信濃國安曇郡 川會神社 |
長野県の池田町にある。
大糸線・安曇追分駅の北東2Kmほどの会染十日市場に鎮座。
高瀬川にかかる高瀬川を東へ渡って100mほどで北上すると
目の前に、社域の森が見えてくる。
長い参道を北へ進むと、森の入口に鳥居。
鳥居扁額には「延喜式内 川會神社」と刻まれている。
鳥居をくぐると、広い境内。
参道正面に額殿(神楽殿)があり、
その後方に少し離れて拝殿。
拝殿の後方にブロック垣に囲まれて流造の本殿がある。
参道脇にはブランコや滑り台などの遊具が並んでおり
周囲の子供の遊び場になっているのだろうか。
境内周囲は、木々に囲まれ、
周囲から隔絶された神域という雰囲気。
天気が良くて、木漏れ日の影のため、写真撮影は失敗。
こういう神社は曇天か朝一の参拝が良いのだが。
創祀年代は不祥。
社伝によると、景行天皇の御宇、
有明の里(安曇の郷)の草創の神を祀った神社であるといい
式内社・川會神社に比定されている古社。
川會の社号は、犀川の支流・高瀬川と
木崎湖より発する農具川の合流地点に祀られたことによる。
元は川の中島にあったのだろうか
嶋の大明神とも称され、
往古は現社地の北西80mの宮地(字嶋ノ宮)に鎮座。
白鳳二年(673)社殿建て替えが行われたが、
天永元年(1110)高瀬川の氾濫によって流出し
永久三年(1115)九月、東方200mの地(字古宮)に遷座。
安永七年(1778)再度流出し、
天明三年(1783)現社地に遷座されたという。
当社の縁起書によると、
景行天皇の頃、当地は湖沼であったらしく
湖水に白毛の犀が住んでいたが、
高梨に棲む蒼犀と結婚し、一子「和泉の真郎」を産む。
「和泉の真郎」が成長し、母犀に会いに来たところ
父母の名前は「底津彦、底津姫」であると教えられる。
そして、母犀の背に乗り、岩を砕いて、湖水を川に流して
陸地とし、有明の里とした。
「和泉の真郎」はそこに館を立てて一子を生み
「和泉の太郎」と名づけた。
「和泉の太郎」は、山岳洞窟に棲む妖鬼を退治し
村人の暮らしを守ったが百歳で神去り、
河會明神となったという。
この話は、安曇の伝説「日光泉小太郎」の話と同じもの。
日光泉小太郎では、母犀は諏訪大明神の化身となっているが
当社では底津綿津見命となっているようだ。
社殿の脇に、以下の境内社六社が祀られている。
秋葉社、大神宮、諏訪社、戸隠社、八幡社、天満宮。
拝殿の向拝屋根に三つ巴の紋が付いていたが、
本殿の幕には五七の桐紋が染められていた。
社域の森 |
 |
鳥居  | 神楽殿  |
本殿  | 拝殿  |
境内 |
 |
境内社  | 境内  |
志きしまの道ハ あまりにひろければ 道ともしらて 人や行くらん −境内由緒書− |