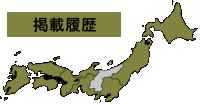[HOME] >
[神社記憶] >
[甲信越地方] > [HOME] >
[神社記憶] >
[甲信越地方] >
|
|
|
根古屋神社
ねごやじんじゃ
山梨県北杜市須玉町江草5336

|
|||
山梨県北杜市にある。
中央道須玉I.C.の北東7Kmほどの江草に鎮座。
塩川ダムへ向かう601号線が23号線に合流するあたりで、東へ入った場所に境内がある。
境内全体は塩川に面している、というより塩川左岸にある道に面して北西向き。
鳥居の脇に祭神の名「天兒屋根命」と刻まれた石柱が立っており
鳥居の扁額には「根古屋大明神」。
鳥居をくぐると左手すぐに神楽殿、正面に拝殿がある。
拝殿の後方の本殿は、覆屋根の下で撮影が難しいが、
こけら葺きのような流造だった。
境内はあまり広くないが、境内左右にある二本の巨木で有名な神社。
国指定天然記念物の「根古屋神社の大ケヤキ」と呼ばれており、境内案内板では樹齢800年。
(『平成祭データ』では凡そ一千年前後、『山梨県神社誌』では千数百年とある)
向って左の欅が田木(田樹)、右が畑木(畑樹)で、
毎年、田木の方が早く芽吹くと稲作が、畑木の方が早いと畑作物が豊作になるという。
武田安芸守信満の三男、江草兵庫助信泰の居城、獅子吼(ししく)城の北西麓に鎮座。
城の守護神として斎き祀られた神社。
獅子吼城は、古くは江草城、江草小屋とも呼ばれ、地元では城山と呼ばれている城跡。
江草城が落城する時、城内の怪物(獅子)が吼えながら深い淵に飛び込んだと伝えられ、
それ以後、当地では正月の獅子舞や、子供の玩具としての獅子も禁じられ、
禁を破ると暴風雨になるという。
当社の神紋に関して、
本殿屋根に五三桐、拝殿屋根に菊紋と武田菱の金飾りが付けられており、
どれが当社の神紋か確認できなかったので、全部載せておいた。
本殿のものが正しいような気もするが。とりあえず全部。
社前、左に田木、右に畑木 |
 |
田木  | 畑木  |
神楽殿  | 拝殿  |
社殿横から  | 本殿  |
|
やまなしの歴史文化公園「のろしの里 すたま」 根古屋神社〜獅子吼城跡
獅子吼城は、塩川左岸にある、標高788メートルの独立峰を利用した
お城です。古くは「江草(えぐさ)城」「江草小屋」ともいわれ、地元で
は、城山(じょうやま)と呼ばれています。昔、江草城が落城のおり、城内に住んでいた怪物が野山を揺るが す声で吼えながら眼下の深い淵(獅子淵)をめがけて飛び込み、岩と なってしまったとの伝説から「獅子が吼える城」と書いて、獅子吼城 と呼ばれるようになりました。また、これより、この村では正月の 獅子の舞が禁じられ、これを犯すと暴風雨が起こるとされ、さらに は子ども等の玩具でさえも獅子は許されないと伝えられています。 この城にまつわる最期の記録は、武田家が滅亡後の天正壬午(て んしょうじんご)の乱(1582年)で、甲斐の国を駿河の徳川家康 と相模の北条氏直が争った時でした。たてこもる北条軍に対して、 服部半蔵ひきいる伊賀組と武田家の旧家臣団が夜襲をかけて落城さ せました。この戦いが徳川の甲斐支配を決定的とした合戦でした。 これが甲斐の国で記録に残る戦国時代最後の戦いです。 「根古屋」は、山上に城のある城下町という意味です。 根古屋神社前の道は、長野県佐久や群馬県の地方を結ぶ、小尾街道 または。穂坂路とよばれた古道です。交通の要地でしたから関所も おかれていました。 神社境内にある国指定の天然記念物「根古屋神社の大ケヤキ」は、 別名「田樹畑樹(たぎはたぎ)」と呼ばれる2本の巨樹です。田樹 が早く芽吹くと水田が、畑樹が早いと畑の作物が豊作になるとの言 い伝えがあります。 −境内説明文− 根古屋神社 天然記念物(国指定)、根古屋神社の大欅 昭和33年5月15日指定 欅の巨木で、北側にあるものを田木といい、南側にあるものを畑木といって年によって芽の出方に遅速があり、田木が早く芽を出す年は稲作、畑木が早く芽を出す年は畑作が豊作であることから、田木畑木の名が起こった、両樹の樹齢は凡そ一千年前後と推定され、欅の巨木が2本あることでは、日本一と云われている。
−『平成祭データ』− |
【 根古屋神社 (北杜市) 】