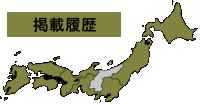[HOME] >
[神社記憶] >
[甲信越地方] > [HOME] >
[神社記憶] >
[甲信越地方] >
|
|
|
鉾衝神社
ほこつきじんじゃ
山梨県笛吹市八代町米倉御所782

|
||
式内社 甲斐國八代郡 桙衝神社 |
山梨県笛吹市(旧八代町)にある。
笛吹市役所八代支社の南1Kmほどの八代町米倉に鎮座。
浅川のかかる米倉橋の北詰、川の土手のような道に参道入り口があり、
土手なので、少し下って境内がある。
参拝日は十一月三日。
参道には数台の車が止まり、なにやら境内が賑やかな雰囲気。
参道を下ると、境内一面にブルーシートを敷いた座席が作られ、
境内右手の舞台では人形芝居(人形浄瑠璃?)の真最中。
どうやら秋季例祭の日だったようで、近所の氏子の方々が集結しているようだ。
いつもは静かな境内なんだろうが、今日は特別。
余所者なので、邪魔にならないように、軽く参拝し撮影開始。
いつものようにウロウロとしたり、佇んだりは出来なかったが
貴重な民俗文化財に触れて得した気分。
太夫、三味線は裃を着け、人形遣いの黒子の衣装も本格的なものだ。
演じられていたのは、三番叟のようだったが、詳しくは知らないのだ、
銅板葺入母屋造の拝殿にも幕がかけられ、華やかだった。
拝殿の後方の本殿は、同じく銅板葺の流造。
境内の案内によると、明治三十四年の再建らしい。
仁徳天皇四年四月の勧請と伝えられる古社。
中世には矛立明神、鉾立明神とも称したが、
明治元年、現社号・鉾衝神社に戻したという。
式内社・桙衝神社に比定され、武田家累代鎮城の社として崇敬され、
特に米倉家の氏神として、度々の修繕が加えられたという。
祭神は、天鈿女命。
猿女君の遠祖であり、天岩戸の前で、矛を持って歌舞したことにより、
「鉾衝」の社号となったという説があるらしい。
明治六年、郷社に列し、
本殿背面の御神木は「鉾衝神社けやき」として
昭和三十六年十二月、県指定天然記念物に指定されたが
昭和五十年の台風で倒れてしまい、指定は解除された。
神紋は、社殿屋根や拝殿の幕などに付けられていた隅切角に花菱の紋。
人形芝居の舞台の後方に、境内社が一つ。
屋根に「太」の文字の紋が付けられていたので、大神社だろうと思う。
案内には、他に稲荷社、天神社、阿夫利神社、蚕影神、道祖神が祀られているとあるが
人形芝居に気を取られて見逃したかもしれない。
蚕影神と道祖神は石(石碑)のようだが。
また、『平成祭データ』には護国神社の名も記されている。
参道入口  | 境内  |
拝殿  | 本殿  |
境内では例祭の真最中 |
 |
人形芝居  | 境内社(大神社)  |
人形芝居 |
 |
人形の頭 |
 |
|
鉾衝神社
所在地 八代町米倉七八二番地
仁徳天皇四年(四二四年頃)の創立と伝えら
れ、御祭神に天鈿女命を祀る町内唯一の延喜式
内社である。昔は源家代々の祈願所として隆盛
し、武田家の頃は米倉氏により社殿等が整えら
れ、徳川時代には歴代将軍の尊崇を得て神領の
寄進を受けていたことが伝えられる。幕末の頃、
災火にあい社殿、宝物、古文書等を焼失したが、
明治三十四年に現在の社殿が再建された。境内
に大神社、稲荷社、天神社、阿夫利神社、蚕影
神、道祖神等が祀られている。本殿裏には山梨県指定天然記念物の樹齢八〇 〇年と言われた大ケヤキがあったが落雷等によ り枯死し、昭和五十六年に指定解除となった。 本殿東に八代町指定有形民俗文化財の米倉に昔 から伝っていた人形芝居の用具保存庫があり、 あやつり人形の頭四十二及び衣装道具一式と三 番叟の人形三体が保存されている。 −境内案内板より− |