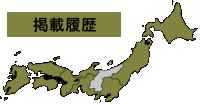[HOME] >
[神社記憶] >
[甲信越地方] > [HOME] >
[神社記憶] >
[甲信越地方] >
|
|
|
国分神社
こくぶじんじゃ
長野県上田市国分1166

|
||
旧郷社 |
長野県上田市にある。
しなの鉄道・信濃国分寺駅の北100mほどの国分に鎮座。
駅を出て18号線を渡った丘の上にあり18号線からも見える場所。
坂道を登ると石組の上に境内がある。
信濃国分寺駅のそば、18号線の横に信濃国分寺跡があり、
当社は、その国分寺跡を見下ろす位置に鎮座していることになる。
そのためか、境内入口は国分寺跡方向の北西向き。
階段を登ると石鳥居が建っており、扁額には「八幡宮」。
鳥居の左脇には「国分神社」と刻まれた社号標。
鳥居の奥に社殿があり、
拝殿は瓦葺入母屋造。後方の本殿は覆屋根の設置された流造。
本殿の右手には、上部が切断された御神木。
御神木にも屋根が設置されている。
明治初年まで、社殿の左右に高さ五丈の老松があったが
暴風の為、中ほどから折れてしまったという。その老松だろうか。
参拝は年末の晴天の日の午後。
境内を吹き抜ける風は冷たかったが、青空がとても綺麗だった。
創祀年代は不詳。
天平年間、信濃国分寺創建と同じ頃の創祀、あるいは再建と伝えられる古社で、
国分寺守護の国分八幡宮。
国分寺・堀・上沢三村の産土神で、通称は八幡さま。
明治までは八幡社と称していたが、明治十一年八月、国分神社と改称した。
古代、当地に弓削(弓作り)の専門集団が居住しており、
弓矢の神として、当社を崇敬し、、社地は広大であったという。
『続日本紀』には、大宝二年に信濃國から梓弓一千張が献上されたとある。
建久八年、源頼朝の請願によって国分寺が再建された時、
同じく当社社殿も再建され、社領は三十石を有していたが、
元和年中社家が途絶えて衰微したという。
明治六年四月郷社に列した。
境内の左手に境内社が二社。
左の境内社には「三峯神社」と扁額付きの鳥居があったが、
右の境内社に関してはわからなかった。
拝殿の屋根に、巴紋が付けられていた。
八幡宮なので八幡の代表紋、三つ巴が神紋なのだろう。
社頭  | 西側鳥居  |
石組上の鳥居と境内 |
 |
拝殿  | 本殿  |
境内 |
 |
三峯社  | 境内社  |
信濃国分寺駅の近く、18号線の南側に
信濃国分寺跡・信濃国分尼寺跡があるが、
しなの鉄道の線路が、国分寺(僧寺)を斜めに横断しており、
国分寺跡の大部分は線路の北側、
国分尼寺跡の大部分は線路の南側にある。
国土安穏・万民豊楽を祈願するとともに文化の興隆をはかって、
天平十三年(741)の聖武天皇の詔により、
諸国に金光明経・法華経を安置した寺院が創建された。
僧寺を金光明四天王護国之寺、尼寺を法華滅罪之寺と称し、
全国六十六ヶ国と壱岐・対馬の二島に国分寺が建立された。
奈良の東大寺が総国分寺として位置づけられ、
国を挙げての大事業であったという。
上田に建てられた信濃国分寺は比較的早い時期に完成。
発掘調査により、僧寺・尼寺ともに当時の伽藍配置や規模がほぼ明らかになっている。
東にある国分寺跡(僧寺、金光明四天王護国之寺)は、
100間(約178m)四方の寺域に
南大門・中門・金堂・講堂・回廊・塔・僧房の建物跡があり、
西の国分尼寺跡(尼寺、法華減罪之寺)は、
80間(約148m)四方の寺域に
南大門・中門・金堂・講堂・回廊・経蔵・鐘楼・尼房・北門などの跡が発見されている。
信濃国分寺跡 |
 |
信濃尼国分寺跡 |
 |
現在の信濃国分寺は、国分寺跡の北方300mの位置にあり、
上田市では、信濃国分寺の俗称である八日堂の名前の方が有名。
天平年間に創建された国分寺は、
939年の平将門の乱(天慶の乱)により焼失し、移転したという。
その後、律令制度の崩壊にともない国家の保護を失った国分寺は衰退し、
鎌倉時代以降に復興再建された。
国分寺境内の三重塔は、源頼朝発願と伝えられ
建久八年の墨書きがあったとされるが、
様式上、室町中期の建立と推定され、明治四十年に国宝に指定された。
現在の信濃国分寺本堂(薬師堂)は
天保十一年(1840)起工、万延元年(1860)竣工されたもの。
現在の国分寺山門  | 国分寺本堂  |
信濃国分寺三重塔 |
 |