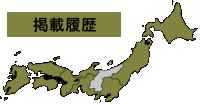[HOME] >
[神社記憶] >
[甲信越地方] > [HOME] >
[神社記憶] >
[甲信越地方] >
|
|
|
船形神社
ふながたじんじゃ
山梨県北杜市高根町小池280

|
||
山梨県北杜市にある。
中央本線長坂駅から東へ直線距離で5Kmほどの高根町小池に鎮座。
32号線を東へ進み、中央自動車道を越えて、五町田交差点から28号線を南へ。
2Kmほど南下したあたりで東へ入った場所に境内がある。
車道は当社境内の後方、北側を東西に走っており、
地図で見ると、境内の南側で小さな川が合流しているのだが、
川が枯れているのか水量が少ないのか、参拝時には川に気付かず、
云われてみればそうだったかも、という感じの川。
その二本の川が合流して作る三角形の土地、船の舳先のような境内。
車道が後方北側を走っているが、境内全体は南を向いており、表参道も南側。
仕方がないので境内を一度通過して南側から入り直して参拝した。
境内入口には木製の両部鳥居。
鳥居をくぐって緩やかに参道を上ると、二基の灯籠と社殿がある、そんな簡素な神社。
拝殿は入母屋造、本殿は流造。
創祀年代は不詳。『甲斐国志』に、
諏訪明神、小池村御朱印社領五石一斗余、相伝えて船形の神社とあるらしい。
また、上下明神を祀るともあり、上宮は建御名方命、下宮は事代主命を鎮斎するとも。
往古は池辺船形山(現在のどこかは未確認)に鎮座していたが、
天正年間(1572〜 1592)に現在地に遷座。
安永元年(1772)の火災により、古記録等はすべて焼失した。
『山梨県神社誌』には「古くは式外の古社」とあり、
『三代実録』元慶八年(884)十二月十六日に、
「甲斐国正六位上船形神従五位下」とある国史見在社ということだろうか。
六月晦日に行われる当社の「夏越祭」、茅輪くぐりは北杜市指定無形民俗文化財に指定されている。
以下の「唱え言葉」を唱えながら、左回り、右回り、左回りに茅輪をくぐる。
「六月(みなつき)の夏越(なご)しの祓(はら)いする人は 千歳(ちとせ)の命延(の)ぶというらむ」
「思うことみなつきねとて麻の葉を 切りに切りても祓(はら)ひつるかな」
「船形の神の御前に身曽貴(みそき)して 憂(う)きことこぞ六月(みなつき)の空」
拝殿の屋根などに九枚笹の紋が付けられていた。
「平成祭データ」によると、境内社が稲荷社外九社とある。
社殿後方に並んだ小さな石祠のことだと思うが、詳細は未確認。
社頭 |
 |
鳥居  | 境内  |
境内 |
 |
本殿  | 境内社  |
境内社殿 |
 |
|
高根町指定無形民俗文化財第五号 小池船形神社の茅輪くぐり
平成四年 二月十八日 指定
−境内説明文より− 船形神社 鎮座地 山梨県北巨摩郡高根町小池280 御祭神 建御名方命 事代主命 由緒 甲斐国志によると諏訪明神、小池村、慶長8年(1603)徳川氏より御朱印社領5石1斗余、社地1440坪を寄進され、相伝えて船形神社と称す。上下明神を祀る。上宮は建御名方命を、下宮は事代主命を鎮斎する、往古は、池辺船形山に鎮座す。船形神前池田など云う処あり。天正中(1573年〜1592年)に今の地に移すと記されている。現在社名は船形神社となっているが、古くは、式外の古社であったが、安永元年(1772)類焼の災に遭い、古記録等焼失したと云う。 例祭日 春4月10日 秋10月10日 祭 日 夏越祭 6月30日(夏越祓、茅の輪くぐり) 社 殿 神殿、覆屋、拝殿、鳥居、石燈籠 境内社 稲荷社外9社 社 地 境内1反6畝 山林1反5畝 氏 子 46戸 −「平成祭データ」− |