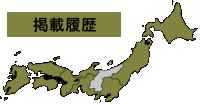[HOME] >
[神社記憶] >
[甲信越地方] > [HOME] >
[神社記憶] >
[甲信越地方] >
|
|
|
子檀嶺神社 中社
こまゆみじんじゃ なかしゃ
長野県小県郡青木村大字田沢

|
||
式内社 信濃國小縣郡 子檀嶺神社 |
長野県上田市の隣、小県郡青木村。
143号線が12号線と合流する場所にある
青木村役場から、西へ2・3Km進み、川沿いの右脇道へ侵入。
公民館あたりで、田沢川を渡ると、民家の間に鳥居がある。
鳥居をくぐって、山へ続く道(参道)を登っていくと、
森の前に鳥居が見える。そこが境内。
上の写真は、境内から鳥居を見たところ。
当社の北方1Kmにある子檀嶺山(1223m)山頂に奥社があり、
当社の南、田沢温泉への途中に里社。
当社は中社にあたる。
つまり三社の総称して子檀嶺神社という。
ただし、江戸時代には中社をかんにや小社、小檀大明神、
当社里社を諏訪大明神、大明神とも称し、
三社合わせて諏訪大明神と称していたらしく、
明治十四年四月二十日に子檀嶺神社と改称された。
祭神は木俣神とされているが、三代実録では駒弓神とある。
当地周辺は信濃十六牧の一つ塩原牧に属し、
馬の産地でもあり、牧場の守護神とも考えられている。
子檀嶺山山頂に奥社を持つ神社は、当社の他に、
村松神社、子檀神社と三社ある。
ということで、式内・子檀嶺神社はそれら三社の総称、
子檀嶺山を御神体山とする神社の総称である可能性もあるらしい。
川側の鳥居をくぐって参道を登っていると、
ちょっとした丘があり、丘上につづく道に鳥居がある。
登ってみると枯葉の境内に小祠が祀られていた。
当初、これが中社なのかと思ったが、社殿には八幡宮とある。
付近の方にお聞きすると、やはり八幡宮だった。
中社は、そこからまだまだ上に登った場所になる。
参道をさらに進むと、高い木々に囲まれた森がある。
日陰の森の向うに、日に輝いた子檀嶺山が見える。
参道から見た子檀嶺岳(1223m) |
 |
田沢川に面した鳥居  | 境内入口  |
境内参道と舞殿  | 境内から舞殿  |
境内 |
 |
拝殿  | 拝殿  |
本殿  | 本殿後方から  |
境内社  | 境内社と石祠  |
|
當社については、三代實録貞観二年(八六○)二
月五日「駒弓神」が従五位下に叙せられたとあるのが初見
である。しかし東山道が大字田澤中挾組を通つてをり、又
前述の鹽原牧・浦野驛との開係からしても、古くから鎮座
してゐたと推定される。延喜期より室町時代末までの動向
は不詳であるが、江戸時代には諏訪大明神、明治十四年か
らは式内子檀嶺神社として崇められ、昭和二十年十二月に
は、縣社に列せられてゐる。 當神社の奥社が子檀嶺岳の頂上に鎮座してゐることは前 述したが、ここに奥社を持つ社は三社ある。岳の南東の麓 の集落に鎮座する村松神社と、東の麓の集落に鎮座する子 檀神社である。上田藩へ上申の『寶永指出帳』によればそ れぞれ「冠者宮ノくわじや明神」と記されてゐる。この子 檀神社の鎮座する地域ノ字・管社に胡麻を作つてはならな いとの言傅へが有る。これは、此の神が葦毛の駒に乗りて 立谷坂にて落馬し、胡麻穀で眼を突き傷つけたるを忌みて のことであるとされるが、この古傅は、官社だけでなく、青 木村全域で守られてをり、胡麻忌「コマイム」の信仰は、 子檀嶺岳を取り圍む廣い地域に有つたものと推察される。 −『式内社調査報告』− |
参道途中の丘にあった八幡宮は
枯葉の境内にある小祠で、なんとも秋の風情で良い。
参拝は秋の午後だったため、奥社へは登らなかった。
麓の民家で、話をうかがったが、
「きついよ」と云われて止めた。たまに熊も出るらしい。
参道途中の八幡宮 | |
 |  |