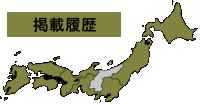[HOME] >
[神社記憶] >
[甲信越地方] > [HOME] >
[神社記憶] >
[甲信越地方] >
|
|
|
船形神社
ふながたじんじゃ
山梨県北杜市高根町長澤2606

|
||
式外社 船形神 三代実録 |
山梨県北杜市にある。
中央本線長坂駅の北東9Kmほどの高根町長澤に鎮座。
141号線(清里ライン)の長沢交差点から西へ700mほどにある丘が境内。
境内入口は道路に面して南向き。
入口に鳥居は見当たらず、参道階段を上ると「郷社舩形神社」と刻まれた社号標が立っている。
さらに参道を進むと鳥居があり、さらに進むと神門。その奥に社殿のある境内がある。
境内の右手に神楽殿、左手に社務所などがあり、正面に拝殿。
拝殿は瓦葺入母屋造。後方の本殿は白い覆屋の中で確認できなかった。
参拝は四月の後半。桜の花は散り始めている時期だが、境内にはまだ少し咲いていた。
終わりゆく春の天気の良い昼下がり。
創祀年代は不詳。一説に、
日本武尊御東征のみぎり、酒折の宮より科野国の国坂の神に事向け給う時、
この地に奉幣した伝えられる古社。
長沢東井出集落の氏神として崇敬され、もとは諏訪明神と呼ばれていたが
社地が船山といって、船形神社と称するようになったといい、
仁壽元年(851)甲斐守小野貞守の祈願により社頭を造営。
『三代実録』元慶八年(884)十二月十六日に、
「甲斐国正六位上船形神従五位下」とある国史見在社。
康和元年(1099)、新羅三郎義光が社殿を改築。その後武田家代々社頭を修造。
当社は甲斐信濃の境に位置し、武田信玄公が信越へ往来の都度、武運長久を祈願。
永禄年中信玄より神領二石八斗を寄進され、徳川時代朱印地を許された。
明治五年郷社に列した。
『全国神社名鑑』には、当社の神紋は割菱とあり、
拝殿の屋根や参道脇の「神楽殿屋根葺替記念碑」に武田菱(割菱)が付けられていた。
参道脇に石祠が並んでいたが詳細は未確認。
『明治神社誌料』には、当社の境内社として、
大天白社、三峯社、石尊社、小天白社、原山社、疱瘡神社、七鬼社、琴平社、
弁天社、愛宕神社、八雲神社、第六天社、山神社、戸隠社、秋葉社、天神社、
諏訪社、道祖神社、稲荷社の名が列記されている。
社頭 |
 |
参道入口  | 社号標  |
参道  | 参道鳥居  |
神門  | 境内  |
境内 |
 |
拝殿  | 本殿覆屋  |
境内社殿 |
 |
石祠  | 神楽殿  |
|
郷社船形神社の由緒
鎮座地山梨県北巨摩郡高根町字長沢船山二六〇六番地 祭神 建御名方之命 社歴 昔日本武尊命御東征の砌酒折の宮より科野國 國坂の神に事向け給ふ時此の地に奉幣せり。 今尚社辺に口漱ぎ給ひし泉有り文徳天皇時代 仁壽元年(今より凡そ千二百廿六年前)甲斐守 小野貞守の祈願に依り社頭を造営して陽成天 皇時代元慶元年(壬寅)正六位上の当神社に対し 從五位を授く。康和年中新羅三郎義光再建し 其後武田家代々社頭を修造す。当社は甲斐信 濃の境に有るを以って武田信玄公信越へ往来 の都度武運を祈願せりと云ふ。永禄年中信玄 より神領貮石八斗餘を給はり爾来徳川家代々 より朱印地を許されたり。 明治四年官令有り悉く上知して同六年巨摩郡 第十四區郷社に編入せらる。 明治四十年神饌幣帛料の供進神社に指定せら れたり。 −参道由緒書きより− |