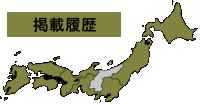[HOME] >
[神社記憶] >
[甲信越地方] > [HOME] >
[神社記憶] >
[甲信越地方] >
|
|
|
弓削神社
ゆげじんじゃ
山梨県西八代郡市川三郷町市川大門6373

おのずから心も清しみしめ縄 弓削の社の神垣のうち
|
||
山梨県の市川三郷町にある。
身延線・市川大門駅の南東500mの市川大門に鎮座。
市川大門とは、当社の大門から付けられた地名だという。
409号線を南下し、鳴沢川を越えて西へ進むと
西向きの境内入口がある。
数段の階段をあがり、朱の鳥居をくぐると境内。
参道の先に神門があり、
参道の左手には小さな石祠が祀られてている。
神門をくぐると一段高い境内。
樹齢八〇〇年の白檀の御神木があるが、
江戸時代の落雷で焼失し、根元のみ。
境内の奥に瓦葺の社殿(拝殿)があり、
後方には流造の本殿。
本殿の屋根、通常の家の鬼瓦の位置に、
鬼の面のようなものが付けられている。
参拝は十一月の休日の朝。
朝なので、西向きの入口から太陽へ向って歩いて参拝。
この日は、例祭の翌日だったようで、
境内には注連縄飾りなどが残っていた。
通称は、二の宮さん。
これは甲斐国の二宮ではなく、市川郷の二宮。
市川郷の一宮は、一宮浅間神社で、
当社の南西500mほどの位置にある。
創祀年代は不詳。
社伝によると、日本武尊が東夷平定の帰路、
大伴武日命が当地に留まったが、
その館跡が当社であるという。
大伴武日命は、日本武尊より「靱部」を賜ったことから
靱部社=弓削社となったという。
『日本後記』延暦二十四年(805)十二月二十日の条に
「甲斐国巨摩郡弓削社預二官社一。
以レ有二霊験一也。」
と記載されている。
式内社・弓削神社に比定されている古社であるが
延喜式では八代郡にあると記されており
日本後記の巨摩郡とは異なっている。
これは、当地が八代郡と巨摩郡の境にあり
記載の違いは、郡境の変遷によるものらしい。
また、『続日本記』大宝二年(702)二月二十二日の条に、
「歌斐國献二梓弓五百張一。以充二大宰府一。」
とあり、古代から当地では弓を作っていたようだ。
本殿の右手に境内社が祀られている。
左から白紙社・衢神社・地主社・東照宮・祖霊社。
神紋は、手水鉢や社殿の屋根に付けられていた「剣に抱き弓」。
弓紋は弓削氏系の家紋だそうだ。
境内入口 |
 |
参道の石祠  | 境内参道  |
神門  | 境内  |
境内 |
 |
拝殿  | 本殿  |
手水鉢の神紋  | 本殿の屋根に鬼  |
御神木(白檀)  | 本殿右の境内社  |
弓削神社御由緒
勧請年月は不詳であるが、延喜式所載の甲斐国二十座の内の一社である故少くも今より
千三百年以前の創立である。日本後記に「延暦二十四年(西暦七八二年【八〇五年?by玄松子】)十二月甲斐国巨摩郡弓削神社官社に列す 霊験あるをもってなり」と記載しあり、此辺は古来、八代・巨摩郡両郡の境であったので時 勢の変遷と共に或は巨摩郡に或は八代郡にその所属が異動したもののようである。 景行天皇四十年皇子日本武尊、吉備武彦、大伴武日連を従えて東国を平定し還路 甲斐国に至り、酒折宮に駐留せられた際靱部をもって大伴連の遠祖武日に賜うと伝 えられ、大伴武日命はその後此地に留まり、居館を造営し此周辺一帯を治めたが土人の その徳を慕うもの其子孫と共に本社を創設したもので、社号のユゲはユキベの約に て靱部社と云うが如く、然れば本社の創建は遠く成務仲哀の御宇にありと云 へるのである。 当社の南に弓削塚という古墳あり、その辺の字名を御弓削と呼ぶ伝えて大伴武日命 の墳墓にして当社はその館跡なりとも云はれている。 鳥居の前に老松があり、そのかたちあたかも蟠竜の如く、幾百年を経たものかを知らず、 伝え云う天正十年徳川家康宿陣の際この松を見ていたく愛賞され、その後これを 「御言葉の松」と称し、広く近隣にその名を知られ神社の御神木として敬仰せら れたが惜しくも江戸末期枯死して今は空しくその名を止むるのみである。 甲斐源氏の祖刑部三郎義清市川の郷に館していた時、曾て本社に通夜し左の 歌を詠じた。 「おのずから心も清しみしめ縄 弓削の社の神垣のうち」
明治六年郷社列す。 境内に白紙社あり、天日鷲神・津昨見神を祀る。他に地主社・東照宮・衢神社等の境内社がある。 −境内案内板より− | |||||||||||||||||||||