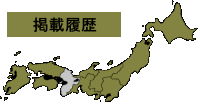[HOME] >
[神社記憶] >
[関西地方] > [HOME] >
[神社記憶] >
[関西地方] >
|
|
|
高野神社
たかのじんじゃ
滋賀県栗東市高野726

|
|||
式内社 近江國栗太郡 高野神社 |
滋賀県栗東市にある。
手原駅の北東2Kmほどの高野に鎮座。
1号線から少し北へ入った場所、野洲川の西に境内。
野洲川の対岸には三上山がある。
地図で確認すると、高野公園の横にあるようだ。
参道入口は南西にあり、鳥居の脇に「高野神社」と刻まれた社号標。
数十mの参道を進むと四脚門がある。
この四脚門は、室町時代、京都御所の門を拝領したものという。
四脚門をくぐり、少し左に曲がると社殿のある境内。
境内中央に瓦葺の拝殿があり、
拝殿の後方、垣に囲まれた流造の本殿が鎮座。
現在の本殿は、寛永七年(1630)修造し
天保三年(一八三二)改築されたもの。
本殿のある垣の外、右手に本殿より少し小振りだが
立派な摂社が二つ並んでいる。
右手にあるのが、当社の二の宮・敏鎌神社。
左が、三の宮・八重釜神社らしい。
参拝は年末の休日。晴天の下の参拝。
創祀年代は不詳。
社伝によると、元明天皇和銅元年の勧請。
高野庄の総社であり、地名を社号としたという。
大同元年、大嘗会の時、
悠紀地方である当地から新稲三束を進貢したので
当社は「由岐志呂宮」「由岐宮」と呼ばれて尊崇されたらしく、
式内社・高野神社に比定されている古社。
敏鎌神社の右手に小さな祠があるのだが、社名はわからない。
『平成祭データ』には境内社として、稲荷神社の名が記されているが
参道の案内には、大神宮と森勝稲荷の名が載っており、
『滋賀県神社誌』には、稲荷神社、大神宮、祖霊社の名があるので、
この祠以外にも、他に境内社があったのかもしれない。
境内には、神武天皇遥拝所の石碑も。
本殿のある垣に中門があるが、
中門にかけられていた幕に、桐紋と巴紋が染められていた。
当社の神紋だろうか。
『滋賀県神社誌』には、桐紋のみが記載されている。
参道入口  | 鳥居  |
参道  | 神門、残念、カーポート状態だった  |
境内  | 社殿  |
中門と垣 |
 |
社殿  | 本殿  |
垣外、右手に摂社 |
 |
三の宮・八重釜神社  | 二の宮・敏鎌神社  |
敏鎌神社の横に小祠  | 神武天皇遥拝所  |
|
高野神社由緒
社伝によると、天智天皇の御代以降、高野造なる人が この地一帯を開墾開発し、高野郷と名付けられ、特に飛鳥 時代、和銅年間(七〇八〜七一四)我が国で最初に鋳造された「和同開珍」 の鋳師(鋳銭司)高野宿彌道経一族が住んだことは有名であり、 それ等の人々の氏神として、祖先を祀ったのが当社である。 中世よりは、通称「由紀志呂宮」又「由岐宮」として 尊崇されて来た。これは大同元年(八〇六)大嘗祭の悠紀方 として新稲を進納したことに由来する。尚、正平五年・ 観応元年(一三五〇)兵災に懸り社殿以下類焼す。氏子等仮殿を 営みて祭祀十年余を経て、貞治(一三六二)・天正(一五三三)・寛永 (一六三〇)と改築修造を重ね天保三年(一八三二)現在の社殿を建立 する。 境内摂社として、土・水を祀る「敏鎌社」(二の宮) 「八重釜社」(三の宮)があり、共に農耕にかかわる大自然 の神々で、本殿・二の宮・三の宮は何れも八角柱状の 神木を御神体とし、御柱の信仰をとどめるものである。 大神宮社は明治三十三年(一八九〇)森勝稲荷社は弘化三年 (一八四六)の夫々の再建であり、拝殿も安政五年の(一八五六)の再建 である。社前の楼門は室町時代の天文二年(一五三二)朝廷 (現京都御所)の門を拝領移築したものと伝う。その際派遣された 別当を松源院と申し爾来当社の坊として、天台宗総本山より も住職を派遣され、又、数々の佛像・経巻等現在所蔵の文化財 の寄贈を受く。尚、明治維新「神佛分離」により境外隣地 に移し更に昭和二十年(一九四五)現地に移築する。 鎌倉時代以降当社に対する武門武士の崇敬篤く祈願奉賽 の事蹟多し。 氏子は古くは五十余ケ村の総社であったが兵災や検地制度に より、又組織上の事情により現在は六ケ村(高野[小坂・土村・今里]・ 六地蔵・梅の木[六地蔵]・林)なり。 −参道石碑− |