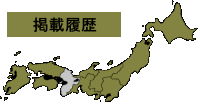[HOME] >
[神社記憶] >
[関西地方] > [HOME] >
[神社記憶] >
[関西地方] >
|
|
|
草岡神社
くさおかじんじゃ
滋賀県長浜市余呉町国安52

|
||
滋賀県長浜市(旧余呉町)にある。
余呉湖の北3Kmほどの国安に鎮座。
365号線から西へ少し入った場所。
天神山の麓に境内があり、境内中央に3本の巨木が聳えている。
境内は、かなり広い広場になっており、
巨木二本の間に階段があって、階段上に社殿がある。
階段と社殿の距離が近く、社殿全体の写真が、うまく撮れなかったので、
2枚の写真を合成してみたが、少し歪になってしまった。
本殿は、拝殿の後方にあり、新しい屋根の覆が設置されている。
中の本殿は、流れ造で、唐破風付き。
本殿はもともと、拝殿の位置にあったが、明治になって後方に移築された。
創祀年代は不明。
一説には、神功皇后が敦賀へ行啓のおり、
武内宿禰を従えて、当社へ参拝されたといわれるほどの古社。
天正年間に、裏山の天神山に秀吉方の砦が築かれた。
このように、当社は以前は、片岡天神社と呼ばれていたお宮。
当時の祭神は、菅原道真と高御産巣日神・神御産巣日神であったが、
明治になって、日子坐王命が追加訂正されたらしい。
式内・草岡神社として、日下部祖神である日子坐王命を追加したのだろう。
境内階段左右に4つの境内社がある。
左手に、毘沙門社・稲荷社。
右手に、秋葉社・金比羅社。
社殿の屋根や賽銭箱に、星梅鉢の紋が付けられている。
天神と呼ばれた頃の名残かもしれない。
社域  | 鳥居  |
境内 |
 |
毘沙門社、稲荷社  | 秋葉社、金比羅社  |
拝殿  | 本殿  |
大きな本殿覆屋 |
 |
|
天神山
草岡神社裏山が天神山。道を挟んで東側
が茶臼山で共に賎ヶ岳合戦当時秀吉が
山路正国らに命じ砦を築かせたが、
目前の行市山に佐久間盛政が陣を築いた
ので堂木山の線まで退いた。−社前案内板− 由緒
天照大御神の御旨のまにまに、神籬の神勅、天壌の神勅を相議りて御授けになり、すべて生命ある万有を生成化育することを御導きになりました。また、むすび(産霊)の御霊力を祟びまつり、背後の山を産霊山と申し、あまつかみ(天神)と申し上げた。つぎに、国造本紀に「淡海の国造は日子坐王命」とあり、姓民録には「開化天皇第三王子彦坐王命」とあり、丹波国より淡海国造となられ余呉の庄の荒廃したるを御覧になり、当地区の開拓、殖産に多大の御盡力になり御神徳を讃え、当社に奉祀御祖神としてあまねく祟敬せらる。今に尚五ケ郷の一宮的存在であるのも故あることなり。住昔、神功皇后敦賀街道御通行の御時、武内宿禰御参詣奉尊され、それよりますます北国街道御通過の折には官民祈願多くなれり。又今から千余年前、村上天皇天暦元年御神威御真徳のあやかり、浦安の国(郷)でありますよう菅原道真公を奉齊することになって、「天満天神」とよび祟拝されるようになれり。明治三年五月、旧領主飯野藩の命で昔の通り「草岡神社」とよぶようになり今市(村)に遥拝地として弐畝拾七歩賜わる。明治九年(一八七六年)十月村社、同十七年(一九〇八年)四月二十九日郷社、並幣帛供進社として指定される。 −『平成祭データ』− |
【 草岡神社 (余呉町) 】