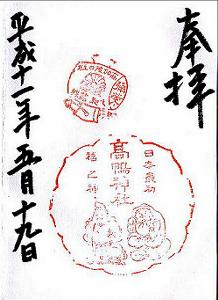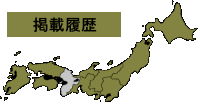[HOME] >
[神社記憶] >
[関西地方] > [HOME] >
[神社記憶] >
[関西地方] >
|
|
|
高鴨神社
たかがもじんじゃ
奈良県御所市大字鴨神

|
|||
|
式内社 大和國葛上郡 高鴨阿治須岐託彦根命神社四座 並名神大 月次相嘗新嘗 |
奈良県御所市にある。
風ノ森峠の西方、葛城鴨神に鎮座。
鎮座地は、通称、捨篠という。
参拝後、ここから御所まで歩いたが結構な距離だった。
五月だったが、汗だくになった。自動車の往来も多く、参った。
式内社・高鴨阿治須岐託彦根命神社四座に比定される古社。
三代実録には、天安三年(859)一月二十七日に、
従二位勲八等高鴨阿治須岐宅比古神と、従三位高鴨神とを
従一位にしたと記されている。
主祭神は、味耜高彦根命(高鴨阿治須岐宅比古神)。
他の三座には、異説もあるが、
現在は妹神の下照姫命、妹婿の天稚彦命、母神の田心姫命を祀っている。
他の説として、阿治須岐速雄命・夷守比売命・天八重事代主命など。
味耜高彦根命は大己貴命の御子神で、迦毛大神とも称される神。
『出雲国造神賀詞』に、大穴持命の子・阿遅須伎高孫根命を「葛城」に、
事代主命を宇奈堤に、賀夜奈流美命を飛鳥へと、
それぞれの神奈備において天皇の守護神としたとある。
味耜高彦根命は、
同じく大己貴命の御子である一言主神と同一視される場合があり
雄略天皇の怒りに触れて、土佐の高賀茂社に流された高鴨神は、
味耜高彦根命あるいは一言主神とされている。
その流されていた高鴨神を、天平宝字八年(764)
加茂朝臣田守を遣わして、当地へ復祀したのが当社。
境内入口の鳥居 |
 |
境内 |
 |
階段上の拝殿  | 本殿  |
境内は広く、東と西に多くの末社が点在している。
ということで、東側から散策。
まず、入口鳥居のそばに朱の祠があるが何だろう。
入口なので祓戸の類だと思う。
境内東側には、市杵嶋姫神社、
住吉三前大神・天照大御神・天児屋根命を祀る東神社、
佐味護国神社、大山咋神社、春日神社、雷神社、
水能波能売命を祀る細井神社、高木大神を祀る西佐味神社などがある。
参道に祠が点在  | 参道に祠が点在  |
東神社 |
 |
市杵嶋姫神社  | 佐味護国神社  | 大山咋神社  | 春日神社  |
雷神社  | 細井神社  | 西佐味神社  | 祓戸社か?  |
境内西側には、八幡神社、一言主神社、猿田彦神社、聖神社、
階段上に稲荷神社、さらに金刀比羅神社、八坂神社、
豊岡姫命を祀る牛瀧神社。多紀理毘売命を祀る西神社がある。
境内 |
 |
西神社 |
 |
八幡神社  | 一言主神社  | 猿田彦神社  | 聖神社  |
稲荷大明神  | 金刀比羅神社  | 八坂神社  | 牛瀧神社  |
東の丘にあたる風の森にある、風の森神社(志那都比古)。
神社だが、祠があるだけなので、ここに載せる。
風の森神社 |
 |
|
高鴨神社 奈良県御所市鴨神。旧県社。祭神は味鋤高彦根命(大国主命の御子神)である。本神社をもって『延喜式』に記載の「高鴨阿治須岐託彦根命神社四座」にあてている。『出雲国造神賀詞』の中に「大穴持命の申し給はく、皇御孫命の静り坐さむ大倭国と申して……己命の御子阿遅須伎高孫根命の御魂を、葛木の鴨の神奈備に坐せ……皇御孫命の近き守神と貢り置きて……」とあって、国つ神である。大田田根子の孫賀茂積命がこの神を奉じて、代々賀茂(鴨)氏が祭祀に当ったが、『続日本紀』天平宝宇八年(七六四)一一月の条に「昔、大泊瀬天皇(雄略天皇)葛城山に狩し給ふ。時に老夫ありて、毎に天皇と獲を争ふ。天皇これを怒りて其の人を土佐の国に流す。先祖の主る神、化して老夫となる。ここに放逐せられる」という経緯があったが、子孫の賀茂朝臣田守と兄法臣円興の奏言によって、淳仁天皇の同年月の七日に、再び土佐から戻して再興されたと伝承されている。葛城系の神は荒ぶる神である。その後、貞観元年(八五九)には従一位にのぼり、『延喜式』では名神大社に列し、祈年・月次・相嘗・新嘗の各条には案上の官幣にあずかった。本神社は別名として拾篠社・上津賀茂社ともいわれ、また本神社を高鴨、葛木御歳神社を中鴨、鴨郡波神社を下鴨とも呼んでいる。なお、本殿(三間社流造・檜皮葺)は天文一二年(一五四三)の再建といわれ重文指定。例祭四月一五日、一〇月一一日。
−『神社辞典』− この地は大和の名門の豪族である鴨の一族の発祥の地で本社はその鴨族が守護神としていつきまつった社であります。 『延喜式』神名帳には「高鴨阿治須岐詫彦根命(たかかもあじすきたかひこねのみこと)神社」とみえ、月次・相嘗・新嘗の祭には官幣に預かる名神大社で、最高の社格をもつ神社でありました。清和天皇貞観元(八五九)年正月には、大和の名社である大神神社や大和大国魂神社とならんで従二位の御神階にあった本社の御祭神もともに従一位に叙せられましたが、それほどの由緒をもつ古社であります。 弥生中期、鴨族の一部はこの丘陵から大和平野の西南端今の御所市に移り、葛城川の岸辺に鴨都波神社をまつって水稲生活をはじめました。また東持田の地に移った一派も葛木御歳神社を中心に、同じく水稲耕作に入りました。そのため一般に本社を上鴨社、御歳神社を中鴨社、鴨都波神社を下鴨社と呼ぶようになりましたが、ともに鴨一族の神社であります。 このほか鴨の一族はひろく全国に分布し、その地で鴨族の神を祀りました。賀茂(加茂・賀毛)を郡名にするものが安芸・播磨・美濃・三河・佐渡の国にみられ、郷村名にいたっては数十におよびます。中でも京都の賀茂大社は有名ですが、本社はそれら賀茂社の総社にあたります。 『日本書紀』によると、鴨族の祖先のヤタガラスが、神武天皇を熊野から大和へ道案内したことが記されています。そして神武・綏靖・安寧の三帝は鴨族の主長の娘を后とされ、葛城山麓に葛城王朝の基礎をつくられました。 この王朝は大和・河内・紀伊・山城・丹波・吉備の諸国を支配するまでに発展しましたが、わずか九代で終わり、三輪山麓に発祥した崇神天皇にはじまる大和朝廷によって滅亡しました。 こうした建国の歴史にまつわる由緒ある土地のため、鴨族の神々の御活躍は神話の中で大きく物語られています。高天原から皇室の御祖先であるニニギノミコトがこの国土に降臨される天孫降臨の説話は、日本神話のピークでありますがその中で本社の御祭神であるアジスキタカヒコネノカミ・シタテルヒメノカミ・アメワカヒコ、さらに下鴨社の事代主神が、国造りの大業に参画されています。 御本殿にはアジスキタカヒコネノカミを主神とし、その前にシタテルヒメノカミとアメワカヒコノミコトの二神が配祀され、西神社には母神のタギリビメノミコトが祀られています。古くはアジスキタカヒコネノカミとシタテルヒメノカミの二柱をまつり、後に神話の影響を受けてシタテルヒメの夫とされたアメワカヒコ、、また母神とされたタギリビメノを加え、四柱の御祭神となったものと考えられます。 現在の御本殿は室町時代の三間社流造の建物で、国の重要文化財に指定されています。なお東神社は皇大神・住吉神・春日神をお祀りしています。 −『平成祭データ』− |