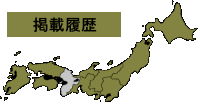[HOME] >
[神社記憶] >
[関西地方] > [HOME] >
[神社記憶] >
[関西地方] >
|
|
|
下鹽津神社
しもしおつじんじゃ
滋賀県長浜市西浅井町集福寺455

|
|||
滋賀県長浜市(旧西浅井町)にある。
近江塩津駅の北2Kmほどの集福寺に鎮座。
8号線から東へ、北陸本線のくぐって、大川沿いに進む。
参道入口に鳥居が立ち、傍らに社号標。
参道を歩くと、目の前に美しい巨木が聳えている。
境内入口に案内板があり、右手が広い境内。
左へ進み社務所の裏手に回ると「五輪塔」がある。
境内の右端に社殿があり、本殿は覆屋の中にあるようだ。
本殿の左横に、小祠・白山社。
その横に二棟並んだ神明社がある。
創祀の由来は、社伝によると、
応神天皇が、皇子の頃、塩土老翁の託宣を得て、
即位の後、大雀命・宇遅能和紀郎子命の二皇子に
この神を崇敬するように命じた。
そこで、二皇子は、淡海の集福蘇翁に命じ、
仁徳天皇三年四月、
浅井郡下塩津郷集福寺小松山小稲森に社殿を創立し、
塩土老翁を鎮祭し、下塩津神社としたという。
醍醐天皇昌泰二年(899)、
今出川大納言の二子で、天台僧の大法深が
当社の社僧に任ぜられ、信仰していた熊野三所権現を勧請し、
伊邪那岐命・伊邪那美命を配祀した。
社殿には、三つ巴・桐・菊の3種の紋が付いていたが、
案内板に、神紋は、菊と桐とある。
このように神紋を記載してくれるとありがたいな。
参道の大きな木 |
 |
境内入口  | 境内左手にある五輪塔  |
境内社殿 |
 |
神明社  | 拝殿  |
白山社  | 鳥居  | 社号標  |
|
式内社 下塩津神社の由緒
第六十代醍醐天皇の昌泰二年(八九九)今出川大納言の子の 天台僧が当社神宮寺の吉祥寺の社僧となり、紀伊の国熊野神社 の伊邪那伎命・伊邪那美命の二神を勧請して熊野三社権現と称 え奉るに至った。下塩津郷五ケ邑並びに境内七町四方を神領と した。永享四年(一四三二)二月従五位の神階を宣下される。 延喜式神明帳に浅井郡十四座とあるが、その中に下塩津神社 とあるのは当社である。
−境内案内板より− |
【 下塩津神社 下鹽津神社 (西浅井町) 】