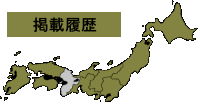[HOME] >
[神社記憶] >
[関西地方] > [HOME] >
[神社記憶] >
[関西地方] >
|
|
|
安牟加神社
あむかじんじゃ
兵庫県豊岡市但東町虫生字箱ノ宮267

|
|
兵庫県豊岡市にある。
但東総合支所の北東6Kmほどの但東町虫生に鎮座。
太田川に沿って、482号線を進み、
赤花川との合流点で2号線へ入り、さらに2Kmほど進んだ場所。
道路から少し入った場所に境内がある。
境内入口には「式内 安牟加神社」と刻まれた社号標が建ち、
階段を上ると鳥居。鳥居をくぐると境内。
境内奥(北側)に石組があり、その上に社殿。
中央に拝殿があり、拝殿の後方に
妻入の春日造のような本殿がある。
拝殿の左右に境内社が一つずつ。(稲荷神社と三柱神社)
鳥居の横、社殿の正面に歌舞伎舞台がある。
参拝は5月の連休の朝。
強烈な朝日を正面に受けながら当社へ向かったが、
あまりに眩しくて、見落としてしまい、
Uターンして戻り、ようやく到着。
Uターンせずに、もう少し進むと京都に入ってしまう場所にある。
創祀年代は不祥。
聖大明神とも称された古社で
式内社・阿牟加神社の論社。
承和十五年(848)秋八月、安牟加首虫生を出石主政に任ず。
安牟加首虫生其祖物部十千根命を虫生の丘に祀る。
これを安牟加神社という。
また、丹波国天田郡・奄我神社から分祀したとの説があり、
祭神は、『姓氏録』に
「奄我(アンガ)は天穂日命の後なり」
とあることから天穂日命とする。
明治六年十月村社に列し、
明治四十二年上宮神社・神明神社を合祀した。
社頭 |
 |
鳥居  | 境内  |
拝殿  | 歌舞伎舞台  |
社殿  | 社殿  |
本殿 |
 |
|
兵庫県指定文化財
安牟加神社 農村歌舞伎舞台
農村歌舞伎舞台は近世から近代にかけて、庶民の厚い共感に支えられた文化施
設だった。農村へ歌舞伎が浸透しはじめるのは江戸時代初期で、十八世紀に入ると地芝 居が農村でも上演されはじめる。寛政十一年(一七九九)江戸幕府は芝居禁止令 を出し、「神事祭礼の際とか虫送り・風祭りなどの名目で芝居・見世物のよう なことを催して見物人を集め、金銭を費やしているのでそのようなことは一切して はならない」として歌舞伎関係者の入村や遊芸・歌舞伎・浄瑠璃・踊り類も厳し く禁止した。 地芝居を催す主体は基本的に村の青年組織である場合が多く、この若者たち が次第に禁令を犯して芝居を強行するようになっていく。但馬では関宮町葛畑 座、日高町堀の手邉座、但東町の虫生座などが知られている。 かつて但馬地方は農村歌舞伎が盛んで、どこの地区にもこの舞台があったが、現 在では舞台の老朽化に伴い急激に減少している。町内では十八棟の農村歌舞伎 舞台が現存しているが、最盛期にはその倍近い四十棟弱であったと推測される。 本町では江戸時代末期から明治時代にかけて盛んに建てられ、神社の境内な どで地方廻りの役者一座や農民自身が歌舞伎などを上演して大人気を博してい たようである。 本農村歌舞伎舞台は「撥転がし」や「遠見機構」、「上段舞台」などさまざま な仕掛けが工夫されており、文化財的にも但馬地方に残る歌舞伎舞台の代表 的なものとして貴重である。 舞台の構造 ●桁行/6665mm ●梁間/4490mm ●軒高/4415mm ●軒の出/1210mm ●屋根勾配/0.50 ●瓦葺(本来は茅葺) ●舞台の高さ/約790mm 常設の上段舞台 ●桁行/3120mm ●梁間/1705mm ●高さ/450mm ※前面框に障子か襖の溝が二本彫られている。 遠見機構 上段舞台の背面に蔀戸のように上下二つ折になっている。遠見と呼ばれる芝居 の背景が提げられる装置であるが、借景として正面に東里ヶ岳全体が美しく見 られるように配慮されている。 撥転がし 舞台の床が前方観客に向かって緩傾斜し、観客に演劇効果を考慮したものである。 墨書痕 文久元年仲夏二五日若狭藩中石井某 建立時期 舞台壁面に残る墨書痕から文久元年(1861)以前と考えられる。 −境内案内板− |
【 安牟加神社 (豊岡市) 】