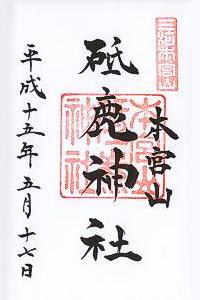[HOME] >
[神社記憶] >
[東海地方] > [HOME] >
[神社記憶] >
[東海地方] >
|
|
|
砥鹿神社 奥宮
とがじんじゃ おくみや
愛知県豊川市一宮町本宮山山頂

|
|||
式内社 参河國寶飫郡 砥鹿神社 |
愛知県一宮町(現豊川市)にある、本宮山(789.2m)山頂に鎮座。
麓から、本宮山スカイラインを上り、
山頂にある駐車場に車を停めると、奥宮までの参道が目に入る。
そのはずだったが、山頂に到着した頃は、霧のため、
何も見えず、駐車場の広さもわからない状態。
右に行けば良いのか、左なのかすらわからない。
そうこうしていると、麓から登って来たハイカーの方に出会い、
奥宮参道まで、一緒に行っていただいた。
駐車場から南側へ歩くと、大きな朱の鳥居。
(でも霧の中)
その奥に、木々の茂った参道が続く。
(でも霧の中)
しばらく歩くと、参集殿のような建物があり、
その前には、大きなお釜と、御神木。
その先の緩やかな階段を登ると社殿がある。
社殿の前には、北側から歩いて登って来る階段がある。
山頂周辺、欝蒼と茂る木々の中をしばらく散策したが、
霧で、視界がゼロ。方向感覚もなくなって来たので、
ゆっくりとはできなかったが、湿った空気によって、
木々が活き活きと、息づいていた。
創祀年代は不詳。
参河國一宮である、砥鹿神社奥宮である。
砥鹿神社は、この本宮山山頂の奥宮と、麓の里宮によって構成されている。
本宮山は古代から信仰の対象であり、
山頂付近には多くの磐座らしきものも多い。
『砥鹿大菩薩縁起』によると、
文武天皇大宝年中、天皇が御病気の時、
「公宣」卿(社家草鹿砥氏の祖)が、
参河國設楽郡煙巌山の勝岳仙人のもとに勅使として派遣されたが、
道に迷い、本宮山に踏み入った。
この時、砥鹿神が老翁の姿で出現し、助けたことにより、
文武天皇の勅願により、本宮山麓に宮居を定めた。
その時、清流に衣を流し、流れ着いた地に社殿を建てたという。
当社は修験道との関係が深く、
『足助八幡宮縁起』には、
「当国寶飯郡大深山(本宮山)ト云山ニ、怪異者三ツ出来セリ、
一ハ猿ノ形、一ハ鹿姿、一ハ鬼軆」とあり、
猿は猿投大明神、鹿は砥鹿大菩薩、鬼は熊野修験者のこと。
参集殿から社殿への階段の側に、
大己貴命和魂を祀る守見殿神社がある。
一月六日に、宝印祭という神事があり、
当社秘伝の宝印が授与されるらしい。
案内にあった宝印は、栗のような宝珠のような形だった。
周囲には、大己貴命荒魂を祀る荒羽々気神社や、
八柱神社、乙女前神社などもあるらしいが、今回は参拝していない。
霧が濃くて、カルピスの中を歩いているようだったから。
霧の中の朱の大鳥居 |
 |
鳥居  | 参道  | 御神木  |
社殿への階段  | 守見殿神社 大己貴命和魂  | 本殿  |
大福釜  | 社殿  |
社殿前の階段 |
 |
|
由緒
本宮山砥鹿神社奥宮の創祀は、文武
天皇大宝年間以前より鎮座さられた事
は、社伝に明らかである(約千三百年以
前)、海抜七八九、二米に位する、本宮山
の秀麗な山姿と全山を覆う樹林は、昔よ
り東海無双の霊域として神聖視され、
殖産の神、護国救人の守護神として広く
尊崇され、明治四年の官制より三河国
唯一の国幣小社に列格された、砥鹿神社
の奥宮である。大神の御神徳は弥々輝き、除災招福、交通 安全、等にも広く御神威を垂れ給っている。
−社殿案内板− |